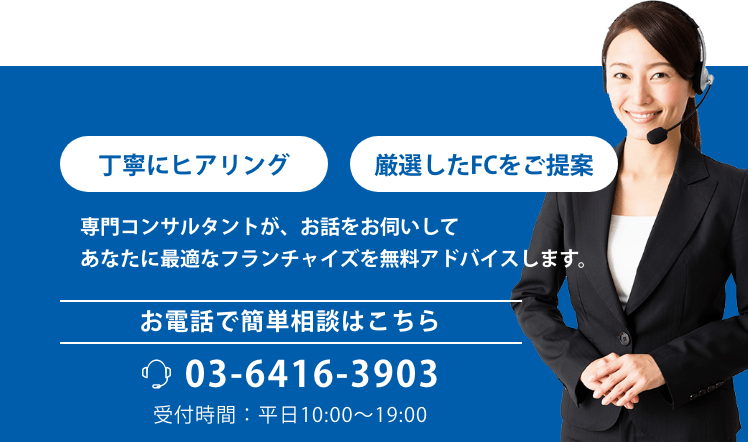フランチャイズ用語集 さ行
-
損益分岐点
損益分岐点とは、売上と費用がちょうど同じになるポイントのことです。簡単に言えば、「赤字でも黒字でもない状態」、つまり利益がゼロになる売上高のラインを指します。このラインを超えると、そこから先は利益が出ていくことになります。
たとえば、ある月の売上が100万円で、経費も100万円かかったとします。この場合、利益はゼロ。つまり、この100万円が損益分岐点です。
ここで注意したいのは、「売上=利益」ではないということです。売上の中から人件費、家賃、水道光熱費、仕入れ費用などのコストをすべて引いたうえで、ようやく手元に残るのが本当の利益です。
損益分岐点を正しく理解するためには、費用の中身を「変動費」と「固定費」に分けて考えることが重要です。
変動費とは
変動費とは、売上の増減に応じて変わる費用のことです。売れた分だけ材料を使い、仕入れや配送も発生するように、売上に比例して増えたり減ったりするのが特徴です。
代表的な変動費には以下のようなものがあります。
- 原材料費・仕入れ原価
- 外注費・販売手数料
- 発送料・配送費
- 接待交際費
- 消耗品費・雑費
たとえば、ハンバーガーが1個売れれば、パンや肉、包装紙などの材料費が発生します。しかし、売れなければそれらの費用も発生しません。このように、売上に連動して増減するのが変動費です。
固定費とは
固定費とは、売上の大小に関係なく、毎月一定額発生する費用のことです。お客様が来なくてもかかる費用、つまり“店を開けるだけで発生する支出”と考えると分かりやすいでしょう。
代表的な固定費は以下の通りです。
- 人件費(社員・アルバイトの給与)
- 家賃・共益費
- リース費用(設備や車両など)
- 広告宣伝費
- 業務委託費
- 減価償却費(設備の長期使用にともなうコスト配分)
フランチャイズ店舗では、どれだけ忙しい日でも、逆に閑散期でも、これらの固定費は変わらず発生します。そのため、固定費の高さ=損益分岐点の高さに直結します。
損益分岐点を下げるには?
利益を出すためには、この損益分岐点をなるべく低く抑えることがポイントです。具体的には次のような工夫が有効です。
- 固定費を見直し、無駄な支出を減らす
- 変動費を最適化し、仕入れロスや廃棄を減らす
- 単価や来店頻度を上げて売上を増やす
たとえば、1か月の固定費が80万円、変動費率が30%の場合、損益分岐点の売上は約114万円になります。つまり、月に114万円を超える売上を出せなければ赤字ということです。
まとめ
フランチャイズ経営で安定して利益を出すには、「売上を増やす」だけでなく、「損益分岐点を正しく理解し、下げる努力をする」ことが欠かせません。
- 損益分岐点とは、利益がゼロになる売上ライン
- 売上から変動費と固定費を差し引いて、初めて利益が残る
- 固定費が多いと、それだけ損益分岐点も高くなる
- 変動費と固定費を理解することで、経営の判断力が高まる
資料請求や開業前の検討段階では、「この業態の損益分岐点はどれくらいか」「本部はどのようなコスト構造で設計しているか」など、数字の裏側に注目することで、より確実なフランチャイズ選びができます。
必要に応じて、図や計算例を使った視覚的な補足も可能です。他の用語のリライトもお気軽にご依頼ください。
-
セントラル・キッチン
セントラル・キッチンとは、フランチャイズチェーンなどにおいて、各店舗で使用する調理済み・加工済みの食材を一か所で大量調理・加工し、集中して供給する仕組み(施設)のことを指します。英語では「central kitchen」、日本語では「集中調理センター」などとも呼ばれます。
このシステムは、飲食業における味のばらつきを防ぎ、調理の効率を上げ、コストを抑えるために導入されることが多く、ファーストフードやファミリーレストラン、コンビニのホットスナック、居酒屋チェーンなど、さまざまな業態で活用されています。
フランチャイズにおける役割とメリット
1. 味の標準化と品質の均一化
フランチャイズでは、全国どの店舗でも「同じ味・同じ品質」で商品を提供することが重要です。もし店舗ごとに調理方法が違えば、お客様の満足度や信頼は下がってしまいます。
セントラル・キッチンでは、統一されたレシピと手順で大量に調理することで、常に一定レベルの品質を保つことが可能になります。たとえば、カレーやラーメンのスープ、ソース、ドレッシング、下ごしらえ済みの具材などを中央で一括製造し、各店舗へ配送します。
結果として、「誰が作っても同じ味が出せる」「新人スタッフでも安定した料理提供が可能になる」という大きな利点が生まれます。
2. 業務の効率化と人件費の削減
各店舗で一から調理する必要がなくなるため、調理工程が大幅に短縮されます。仕込みや調味、加熱などの手間を削減できることで、現場の作業時間を大幅に圧縮できます。
また、調理経験のないアルバイトスタッフでも扱いやすいよう設計されているため、人件費のコントロールやシフトの柔軟性にもつながります。人材の確保が難しい現在、セントラル・キッチンの存在は、店舗運営を支える大きな強みになります。
3. 厨房スペースの最小化と客席の最大化
本格的な厨房設備が必要なくなることで、キッチンのスペースを小さくでき、その分を客席や物販スペースに転用できるというメリットがあります。限られた敷地を最大限活用できるため、家賃対効果を高めることにもつながります。
また、テイクアウト専門店やゴーストレストランといった新しい業態とも非常に相性がよく、柔軟な店舗設計が可能になります。
4. 原価とロスの最適化
セントラル・キッチンでは、仕入れから製造までを一括で管理するため、食材ロスや過剰在庫、廃棄ロスを抑えることができます。また、スケールメリットにより、原材料の一括仕入れによって原価を下げることも可能です。
加えて、温度管理や賞味期限管理なども一元化されるため、食品衛生の面でも安心できる体制を構築できます。
セントラル・キッチン導入時の注意点
セントラル・キッチンには多くのメリットがありますが、導入や利用にはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
- 食材の保存・配送に冷蔵・冷凍管理が必要
- 配送スケジュールや物流コストの把握
- 店舗独自の調理やアレンジが制限される場合もある
- セントラル・キッチンが本部主導か、外部委託かを確認
特に、フランチャイズ本部が自社でセントラル・キッチンを運営しているか、外部工場に委託しているかによって、品質管理や対応の柔軟さが異なる場合があります。
フランチャイズ選びのチェックポイント
フランチャイズに加盟する前には、「セントラル・キッチンの有無」と「その中身」を確認しておくことが非常に大切です。
- どのメニューがセントラル・キッチン対応か
- 食材の納品頻度と方法(冷凍・冷蔵・常温)
- 保存・解凍・加熱方法の詳細
- コスト(仕入れ価格・物流費)が利益にどう影響するか
- セントラル・キッチンが停止した場合の対応体制
これらの情報は、説明会や資料請求時にしっかり確認しておきましょう。
まとめ
セントラル・キッチンは、フランチャイズ経営において「味の安定」「作業の効率化」「省スペース化」「人件費の最適化」という多くの利点をもたらします。見えないところで現場を支える“縁の下の力持ち”のような存在です。
安定した店舗運営を目指すなら、どのようなセントラル・キッチン体制があるのか、どこまで本部が管理・サポートしているのかを必ずチェックしましょう。
長く収益を上げ続ける店舗をつくるための、非常に大きな鍵になります。 -
全店売上高
全店売上高とは、フランチャイズチェーン全体の売上規模を示す指標です。直営店と加盟店の売上をすべて合算した総額であり、そのチェーンがどれだけの市場規模や経済インパクトを持っているかを測るために使われます。
フランチャイズでは、すべての店舗が本部の直営とは限らず、多くは加盟オーナーが個別に経営をしています。そのため、「本部の売上」だけでは全体の実態を把握できません。そこで、直営・加盟の区別なく、チェーン全体の流通金額として全店売上高が重視されるのです。
全店売上高に含まれるもの
会計上の定義として、全店売上高には次のような金額が含まれます。
- 直営店の売上
本部が直接運営している店舗の売上。 - ロイヤルティ(加盟店からの手数料)
売上の一定割合などで徴収される、本部への継続的な支払い。 - 加盟金や研修費などの一時金
新規加盟時に発生する費用。開業支援・マニュアル提供・商標使用の対価など。 - 加盟店への商品・原材料の販売額
本部が食材やパッケージ資材を供給している場合、その売上も含まれます。
これらすべてを合計した金額が、いわゆる「全店売上高」として扱われます。
なぜ全店売上高が使われるのか?
フランチャイズでは、加盟店がそれぞれ独立した法人や個人事業主として運営しているため、本部だけの売上では全体像が見えにくいという特性があります。また、業界によっては店舗ごとの売上を個別に公開していないケースも多いため、チェーンの規模や成長性を把握するには「全店売上高」が最も実用的な指標となります。
たとえば、コンビニチェーンやファストフードチェーンの業界分析、売上ランキング、出店戦略の評価などでも、この全店売上高が用いられます。投資家や取引先、加盟希望者がチェーン全体のパフォーマンスを比較する際にも重視されます。
フランチャイズにおける注意点
全店売上高はあくまで「チェーン全体の規模」を表すものであり、本部の利益や1店舗あたりの収益性とは直接関係しません。たとえば、全店売上高が大きくても、本部の取り分が少なかったり、加盟店の利益率が低ければ、実際の収益性は高くないこともあります。
そのため、資料請求や加盟検討の段階では、「全店売上高」だけで判断するのではなく、以下のような情報も合わせて確認することが重要です。
- 本部の収益モデル(ロイヤルティ、商品供給、サポート費用など)
- 加盟店1店舗あたりの平均売上・平均利益
- 売上が伸びている地域や業態の傾向
- 営業年数・閉店率などの実績指標
まとめ
全店売上高は、フランチャイズチェーン全体の「大きさ」や「勢い」を把握するための指標です。直営・加盟問わず、すべての店舗が生み出す売上を合算することで、チェーン全体の経済的な影響力を知ることができます。
一方で、この数字だけでは見えない部分も多いため、チェーン選びの際には「本部がどう収益を得ているのか」「店舗ごとの利益がどうなっているのか」といった視点も忘れずに確認することが、後悔のないフランチャイズ選びにつながります。
- 直営店の売上
-
セールス・プロモーション
セールス・プロモーションとは、商品やサービスの販売を促進するために行うマーケティング活動全般を指します。略して「セールスプロモーション」や「販促(はんそく)」とも呼ばれ、主に消費者の購買行動を引き出すこと、また流通業者の販売意欲を高めることを目的としています。
フランチャイズにおいても、新商品の導入や集客の強化、季節ごとの売上アップを図る際などに、計画的なセールスプロモーションは欠かせない手段です。
消費者向けセールスプロモーション
消費者に対して直接アプローチし、購買意欲を高めるための施策です。商品の存在を知ってもらい、手に取ってもらうためにさまざまな手法が用いられます。
代表的な手法は次の通りです。
- POP(店頭広告)・什器(商品陳列棚)
目立つ位置に設置し、商品の魅力を視覚的に訴求します。 - ノベルティ(販促グッズ)
購入者に対し、粗品やオリジナルグッズを配布することで購買意欲を高めます。 - 中吊り広告・チラシ・パンフレット
交通機関や新聞、折込などを使って、広範囲に情報を届けます。 - 試食・サンプリング
食品や化粧品などで実際に体験してもらうことで、購入へのハードルを下げます。 - イベント・キャンペーン・クーポン
限定性やお得感を演出することで、来店・購買を後押しします。 - デモンストレーション
商品の使い方や効果をその場で見せることで、理解と関心を深めます。
これらはすべて、「商品を知ってもらう → 興味を持ってもらう → 買ってもらう」までの流れを後押しする役割を持っています。
流通業者向けセールスプロモーション
メーカーが卸業者や販売代理店、小売店などの流通パートナーに対し、自社商品の取り扱いや販売を強化してもらうために行う販促活動です。
たとえば以下のような方法があります。
- 商品情報の提供
カタログ、営業資料、提案書などを使って商品の特徴や優位性を伝えます。 - POPや販促資材の提供
販売現場で活用できるツールを支援することで、取り扱いやすさを高めます。 - まとめ買いによる価格割引
一定数量以上の発注で特別価格を提供し、仕入れ意欲を促進します。 - 販売インセンティブ(報奨金制度)
一定の販売実績に応じて報酬を支払うことで、営業活動を活性化させます。
このような取り組みは、流通との関係性を深めながら、自社商品のシェア拡大につなげる目的で行われます。
セールス・プロモーションの実施ポイント
セールスプロモーションは、単発で行うよりも複数の手法を組み合わせ、計画的に実施することで効果が最大化されます。たとえば、「試食」と「クーポン配布」を同時に行う、「イベント開催」と「ノベルティ配布」を組み合わせる、といった形です。
現在のマーケティングでは、単なる“売るための施策”ではなく、お客様との関係を深め、ブランドへの信頼を築く戦略的なプロセスとして、セールスプロモーションが位置づけられています。
特にフランチャイズにおいては、本部がプロモーション全体を設計し、各加盟店に展開することが多いため、統一感と継続性のある販促計画が成果を左右します。
まとめ
セールス・プロモーションは、「売れる仕組み」をつくるための大切なマーケティング活動です。消費者に向けたものと、流通業者に向けたものの両方をバランスよく行いながら、商品認知と売上を伸ばしていきます。
フランチャイズにおいては、どのような販促支援が受けられるのか、キャンペーンやプロモーションの頻度や実績はどうか――といった視点で本部の体制を確認しておくと、安心して運営に取り組むことができます。
- POP(店頭広告)・什器(商品陳列棚)
-
製品・商標型フランチャイズ
製品・商標型フランチャイズとは、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対して、商標(ロゴやブランド名)と製品のみを提供するタイプのフランチャイズ方式です。販売ノウハウや運営マニュアル、教育プログラムなどは提供されず、店舗運営や販売方法は加盟店側の裁量に委ねられます。
この形式は、1920年代のアメリカで広まった飲料ボトリング業(清涼飲料水の瓶詰め・販売など)をはじめ、自動車やガソリン、家電、タバコなどの分野で普及してきました。
通常のフランチャイズとの違い
フランチャイズには大きく分けて2つのタイプがあります。
- 製品・商標型フランチャイズ
本部から提供されるのは「商品」と「ブランド(商標)」のみ。販売方法や運営は加盟店が自由に決める。 - ビジネスフォーマット型フランチャイズ
商品や商標に加え、販売ノウハウ・店舗運営方法・マニュアル・教育支援なども含まれる。飲食や小売、美容などで主流。
製品・商標型は、いわば「商品とブランドを預ける代わりに、売り方は任せる」スタイルです。一方で、ビジネスフォーマット型は「売り方まで一式パッケージ化して提供する」スタイルです。
製品・商標型が向いている加盟店とは?
このフランチャイズ方式は、販売ノウハウや営業ルートを自社で持っている事業者に向いています。たとえば、すでに流通網を確保している卸売業者、小売チェーン、地域の有力販売店などです。
本部は、自社の商品と商標を広く展開することができ、加盟店はそのブランド力を活かして販売活動を行えます。ただし、接客方法や店内レイアウト、スタッフ教育などは基本的に加盟店に一任されるため、事業経験が浅い人や初心者には不向きな形式とも言えます。
メリットと注意点
【メリット】
- 加盟店の自由度が高く、自社のスタイルで販売できる
- 本部のブランド力や製品力を活用できる
- 独自の販路を活かして事業拡大がしやすい
【注意点】
- 販売方法は自ら考える必要がある
- 成果は加盟店の営業力・経験に左右されやすい
- サポート体制がビジネスフォーマット型よりも薄い
まとめ
製品・商標型フランチャイズは、「売る力」と「販路」をすでに持っている事業者向けのフランチャイズ形式です。商品やブランドの強みを活かしながら、運営スタイルは自分で決められるため、自由度が高い反面、支援が少ない点には注意が必要です。
これからフランチャイズに加盟する場合は、自身の経験や経営力に応じて、製品・商標型かビジネスフォーマット型かを見極めることが大切です。
- 製品・商標型フランチャイズ
-
製造物責任法(PL法)
製造物責任法(Product Liability Law)、通称「PL法」とは、製品の欠陥が原因で消費者に被害が発生した場合、その製品を製造・販売した事業者が損害賠償の責任を負うと定めた法律です。1995年に施行され、製造業や販売業、さらにはフランチャイズにも深く関わる重要な法制度です。
この法律によって、消費者が事故や健康被害にあった際、過失の有無にかかわらず製造者側に責任が問われるため、事業者には高度な安全管理とリスク対策が求められます。
「製造物」とは何か?
製造物責任法における「製造物」とは、**人の手によって製造・加工された動産(動かせるモノ)**を指します。ここには以下のようなものが含まれます。
- 工業製品(家電、機械、部品など)
- 食品や飲料
- 建材や建物(一定の条件で対象)
一方で、形のないサービスや、ソフトウェアのような「動産ではないもの」は、原則としてこの法律の対象外となります(ただし、ソフトが組み込まれた製品は例外もあります)。
「欠陥」とは何か?
ここで言う「欠陥」とは、製品が通常の使用状況で安全に使えない状態を指します。単なる不具合や故障とは異なり、「使用者にとって危険であること」が焦点となります。
欠陥には大きく以下の3つがあります。
1. 製造上の欠陥
製造過程でミスがあり、本来あるべき仕様で製品が作られておらず、安全性が損なわれているケース。
例:設計どおりに部品が組み立てられていない、異物混入、温度管理ミスなど。
2. 設計上の欠陥
設計そのものに問題があり、正しく製造されていても危険性がある場合。
例:電源スイッチが押しにくい位置にあることで誤作動を招く、耐久性が十分でない構造になっているなど。
3. 警告表示上の欠陥
パッケージや取扱説明書などに必要な注意事項・警告が不十分な場合。
例:アレルゲン情報の記載漏れ、誤使用時の危険性についての注意書きがないなど。
これらの欠陥が原因で、消費者が生命、身体、または財産に被害を受けた場合、製造者や販売者は損害賠償責任を問われる可能性があります。
フランチャイズにおけるPL法の関係
フランチャイズでは、本部が開発・製造した商品を、加盟店が販売するケースが多く見られます。このとき、その商品に欠陥があり、消費者に損害が発生した場合、加盟店が責任を問われる可能性があります。
しかし、実際には商品を製造したのは本部であるため、法的には本部が製造物責任を問われることになります。とはいえ、消費者はまず販売者である加盟店に連絡・請求することが多いため、加盟店と本部の間で「求償権(あとから本部に補償を求める権利)」の取り決めを明確にしておくことが重要です。
加盟契約に盛り込むべきポイント
- 商品事故が起きた場合の責任分担
- 加盟店が負担した損害について本部に求償できる条件
- 製造物クレームへの対応フロー(連絡窓口・初動対応など)
- 保険(PL保険)の加入義務や補償内容
本部が明確な対応策を用意していないと、トラブル時に加盟店との信頼関係が崩れる原因になります。そのため、PL法に基づいた安全対策・契約内容の整備は、本部運営の基盤ともいえます。
まとめ
製造物責任法(PL法)は、消費者の安全を守ると同時に、事業者に責任と注意義務を課す法律です。フランチャイズにおいては、本部と加盟店の責任関係が複雑になりがちですが、事故発生時の対応や契約内容を明確にすることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
加盟を検討する際には、「本部の商品がどのように管理されているか」「事故時の対応フローが整っているか」「PL保険に加入しているか」なども、安心して開業するための大切なチェックポイントです。
-
スーパーバイザー学校
スーパーバイザー学校とは、フランチャイズ本部で活躍するスーパーバイザー(SV)を育成するための専門教育機関として、1977年に日本フランチャイズチェーン協会(JFA)によって設立されました。
スーパーバイザーは、加盟店の経営支援や指導を行う現場の最前線として、フランチャイズ本部の中でも非常に重要な役割を担います。そのため、専門的な知識と実務力、そしてコミュニケーション能力が求められます。
資格制度「スーパーバイザー士」
1995年には、より高度な専門性を証明するための「スーパーバイザー士」資格認定制度がスタートしました。この制度では、スーパーバイザーとして必要な知識・能力・現場経験をもとに、筆記試験と面接試験で総合的に評価を行い、基準を満たした受講者を認定します。
この資格は、単なる座学ではなく、フランチャイズの実務に基づいた実践的なカリキュラムと評価が行われるため、信頼性の高い専門資格とされています。
2019年度までに資格を取得したスーパーバイザー士は、累計で約1,300名にのぼり、さまざまな業種のフランチャイズ本部で活躍しています。
フランチャイズにおける意義
フランチャイズ本部にとって、優秀なスーパーバイザーの存在は、加盟店の業績や満足度、ブランドの一貫性を保つために欠かせない要素です。スーパーバイザー学校とその資格制度は、業界全体の人材育成の質を底上げし、フランチャイズ経営の信頼性を高めるために設けられた仕組みといえます。
加盟を検討する際には、「本部にどのような教育体制があるか」「スーパーバイザーの質や研修制度が整っているか」といった視点で比較することが、安定経営の判断材料になります。
-
スーパーバイザー(SV)
スーパーバイザー(SV)とは、フランチャイズ本部の社員として、加盟店の店舗運営を支援・管理する役割を担う人材のことです。本部と加盟店の間に立ち、双方のコミュニケーションを円滑にしながら、店舗の成長と安定経営をサポートする「現場のキーパーソン」といえる存在です。
主な役割と業務内容
スーパーバイザーの業務は業種や本部の方針によって幅広く異なりますが、基本的には次のような役割を担います。
- 経営アドバイス
売上分析、利益管理、コスト改善など、店舗の経営面を支援。 - 運営指導
接客、商品管理、衛生管理、シフト管理など、日々の店舗運営をチェックし、改善点を提案。 - 人材育成支援
店舗スタッフへの教育・研修のサポートや、採用・定着に関するアドバイス。 - キャンペーン・販促活動の推進
本部の販促施策を加盟店に伝え、実施状況をフォロー。 - トラブル対応・相談窓口
クレーム、スタッフ問題、法令対応など、現場での課題を本部と連携しながら解決。
SVは、ただ本部の方針を伝えるだけでなく、加盟店の状況や課題を本部にフィードバックする役割も持っています。そのため、加盟店との信頼関係を築く力や、現場目線での柔軟な対応力が求められます。
専門知識と経験が求められる職種
スーパーバイザーには、担当する業界に関する専門知識や、実務経験、店舗運営に関する幅広い知見が必要です。たとえば、飲食チェーンであれば調理工程や衛生基準、小売業であれば商品陳列や在庫管理など、業態ごとの知識が現場で活きてきます。
また、現場での経験値だけでなく、数字に基づいた経営分析力や、スタッフとの信頼関係を築くコミュニケーション能力も非常に重要です。
呼び方のバリエーション
企業やチェーンによって、スーパーバイザーにはさまざまな呼び名が使われることがあります。たとえば:
- フィールドカウンセラー
- オペレーションフィールドカウンセラー
- ストアアドバイザー
- 店舗コンサルタント など
名称は違っても、基本的な役割は「加盟店の経営と運営を本部とともに支える」点で共通しています。
まとめ
スーパーバイザーは、フランチャイズ経営において現場と本部をつなぐ架け橋のような存在です。加盟店の成功を支える影の立役者とも言えます。
加盟を検討する際は、「SVの数や担当店舗数」「研修・評価体制」などにも注目することで、本部のサポート力や現場支援の質を見極めることができます。 - 経営アドバイス
-
ストアコンセプト
ストアコンセプトとは、店舗がどのような価値を、誰に、どのような方法で提供するかを明確にするための基本的な考え方のことです。店舗づくりや商品・サービスの企画、販売戦略、接客スタイルなど、すべての営業活動の“軸”となる概念です。
言い換えれば、そのお店は何のために存在し、どんな顧客のどんなニーズを満たすのかという“存在意義”を言語化したものがストアコンセプトです。
この考え方は、フランチャイズの出店やブランド開発においても極めて重要で、成功しているチェーンほどこのコンセプトが明確で、一貫性があります。
ストアコンセプトを構成する3つの視点
ストアコンセプトを具体的に考える際は、以下の3つの要素を整理するのが基本です。
1. 「誰に」
=ターゲットの設定
お店が想定している顧客層(年齢、性別、ライフスタイル、職業など)を明確にします。例:20代の働く女性向け、シニア層の健康志向ファミリー向け など。2. 「何を」
=提供する価値の明確化
お客様がその店舗や商品・サービスを通じて得られるメリットや体験価値を定義します。例:時短で栄養バランスの取れたランチが食べられる、安心して子連れで利用できる快適な空間 など。3. 「どのように」
=提供方法や表現手段の設計
価格帯、商品ラインナップ、内装デザイン、接客スタイル、店舗の立地、営業時間など、その価値をどう届けるかの方法を考えます。これら3つがしっかりと連動していれば、店舗のブランディングに一貫性が生まれ、お客様にも強く印象づけることができます。
フランチャイズにおけるストアコンセプトの役割
フランチャイズにおいては、本部が定めるストアコンセプトがすべての店舗に共通するブランドの土台となります。全国どこでも同じ体験を提供するためには、内装や制服、BGM、サービスマニュアルに至るまで、すべてがこのコンセプトに基づいて設計されている必要があります。
また、加盟希望者に対しても、明確なストアコンセプトが提示されていることで「このブランドが誰向けに、どんな価値を提供しているか」が伝わりやすくなり、加盟の判断材料にもなります。
まとめ
ストアコンセプトは、単なるスローガンやキャッチコピーではなく、お店の存在理由と営業戦略の出発点となる大切な考え方です。
- 誰に(ターゲット)
- 何を(提供価値)
- どのように(提供手段)
この3つを明確にすることで、店舗の魅力が伝わりやすくなり、商品開発や販促活動もブレずに展開できます。特にフランチャイズでは、ブランドの統一性を保ち、長く選ばれるチェーンになるための基盤として、ストアコンセプトの精度が問われます。
-
初期投資回収期間
初期投資回収期間とは、フランチャイズ加盟者が開業時にかけた初期費用を、事業の利益によって回収するまでの期間を指します。つまり、「投資したお金を何年で取り戻せるか」を示す重要な経営指標です。
フランチャイズで起業する際には、加盟金や店舗の内装工事費、設備費など、さまざまな支出が発生します。これらを総称して「初期投資」と呼びますが、この金額を事業のキャッシュフロー(手元に残る現金収入)で割って算出するのが、初期投資回収期間の基本的な考え方です。
計算式
初期投資回収期間の目安は、次の計算式で求められます。
初期投資金額 ÷ 年間キャッシュフロー = 回収期間(年)
たとえば、初期投資が1,200万円で、1年間に300万円のキャッシュフローが見込まれる場合、回収期間は「4年」となります。
初期投資に含まれる主な費用
初期投資金額として一般的に含まれるものは以下の通りです。
- 加盟金(契約時に本部へ支払う一時金)
- 研修費(開業前の研修にかかる費用)
- 店舗の保証金、敷金、礼金
- 内装・外装工事費
- 設備・機器購入費
- 店舗設計・図面作成費
- 什器・備品の購入費
- 開業前の賃料(前家賃)
- オープン準備中の人件費(スタッフ給与など)
一方で、本部への預託保証金や販促費用、物件契約時の仲介手数料などは、投資金額に含めないケースもあります。本部が提示する費用の内訳を確認し、誤解のないよう注意が必要です。
フランチャイズ本部の提示値はあくまで参考
多くのフランチャイズ本部では、過去の実績や平均データをもとに「想定される初期投資回収期間」を提示しています。しかし、この数値はあくまでモデルケースであり、実際には店舗の立地や客層、運営者のスキル、競合環境などによって大きく変動します。
そのため、本部のシミュレーションは参考程度にとどめ、自分の計画や見込みに合わせて現実的なシナリオを立てることが重要です。回収期間が読めないまま開業してしまうと、資金繰りが苦しくなり、経営が不安定になるリスクもあります。
投資回収のスピードを見る意味
投資回収期間は、事業の「収益性」や「投資効率」を測るための基準となります。回収期間が短ければ、利益が残る時期も早まり、次の出店や設備投資に回せる資金を早く確保できます。
そのため、以下のような観点で投資回収期間を評価することが大切です。
- 何年以内の回収を目指すべきか(例:3年以内が理想など)
- キャッシュフローの見積もりは現実的か
- 固定費や変動費をどの程度見込んでいるか
- 最悪のケース(売上低迷時)でも資金が持つか
まとめ
初期投資回収期間は、フランチャイズ経営の「安全性」と「将来性」を見極めるための大切な指標です。本部が提示する数値に依存せず、自らの資金計画と現実的な売上見込みをもとに判断することが、長期的に安定した経営を築くための第一歩となります。
加盟を検討する際には、初期費用の内訳や回収見込みの根拠、本部のサポート体制などもあわせて確認しましょう。
-
商標
商標とは、製品やサービスの出所(どこの会社・事業者が作ったか)を示すためのマークやロゴ、文字、デザインなどのことです。たとえば、ロゴマークやブランド名、商品パッケージに記載される名前などがこれにあたります。
消費者が商品を選ぶとき、その商品が「どこで作られたものか」「信頼できる品質か」を判断する材料となるのが商標です。同じカテゴリの商品が多数ある中で、自社の商品を他と区別し、選ばれるための“目印”の役割を果たします。
商標の機能と役割
商標には主に以下の3つの機能があります。
1. 出所表示機能
その商品やサービスが「どこの会社が提供しているか」を明確に示します。
2. 識別機能
似たような商品が多い中で、自社の商品と他社の商品を区別できるようにします。
3. 品質保証機能
商標を継続的に使うことで、「このマークが付いていれば一定の品質が保証されている」という信頼感を消費者に与えます。
フランチャイズにおける商標の重要性
フランチャイズにおいては、本部が保有する商標(ブランド名、ロゴ、店名など)を加盟店が使用することで、全国どこでも同じブランド体験を提供できるようになります。消費者にとっては、知っているロゴや店舗名を見るだけで「安心」「信頼できる」という印象を持ちやすく、集客にもつながります。
加盟契約の中には、商標の使用許諾に関する条項があり、どの範囲で、どのように使用できるかが定められています。
商標と法的保護
商標は、特許庁に出願し「商標登録」をすることで、商標権として法的に保護されます。登録された商標は、他人が無断で使用することができず、使用された場合は差し止めや損害賠償を請求することが可能です。
さらに、商標が広く知られるようになれば、商標登録の有無にかかわらず「不正競争防止法」によって保護されるケースもあります。これは、悪質な模倣やブランドの信頼を損なう行為から守るための仕組みです。
まとめ
商標は単なるロゴやデザインではなく、ブランドの信頼性や価値を支える重要な資産です。特にフランチャイズビジネスでは、商標が加盟店にとっての「営業の武器」ともなるため、その取り扱いや契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。
-
消費者契約法
消費者契約法とは、消費者の利益を保護し、国民生活の安定と経済の健全な発展を図るために制定された日本の法律です。2001年に施行され、主に個人が事業者と契約を結ぶ際に、情報や交渉力で不利な立場に置かれがちな消費者を守るためのルールを定めています。
背景と目的
消費者と事業者の間には、商品やサービスに関する情報の質・量、法的知識、交渉力などに大きな差があります。そのため、事業者による不適切な勧誘や説明によって、消費者が誤った判断をして契約してしまうことがあります。
このような状況を防ぐために、消費者契約法では以下のような権利やルールが定められています。
主な内容と保護のしくみ
1. 契約の取り消しができる場合
事業者が以下のような行為を行い、その結果として消費者が誤認・困惑し契約してしまった場合、消費者はその契約を取り消すことができます。
- 実際と異なる情報を伝える(例:商品の性能を過剰に説明する)
- 必要以上に不安をあおる(例:契約しないと損をすると強調する)
- 重要な事実をあえて説明しない(例:解約条件を伝えない)
2. 不当な契約条項の無効化
消費者にとって著しく不利益となる契約内容については、その一部または全部が無効とされます。たとえば、
- 事業者の損害賠償責任を一方的に免除する条項
- 消費者だけに過度な負担を強いる条項
- 他の消費者の権利を侵害するような内容
このような不公平な内容が契約に含まれていた場合、法的に効力が認められません。
フランチャイズ契約との関係
フランチャイズ契約においては、本部(フランチャイザー)と加盟者(フランチャイジー)は、どちらも事業者という扱いになります。そのため、消費者契約法はこの関係には原則として適用されません。
つまり、加盟希望者が個人事業主であっても、「起業を目的として事業者として契約する」ため、消費者としての保護は受けられないのが通常です。
そのため、フランチャイズ契約では特に以下の点に注意が必要です。
- 契約書の内容を十分に読み込む
- 解約条件や違約金について明確に把握する
- 加盟前に本部の説明内容と実態に差がないか確認する
まとめ
消費者契約法は、一般の消費者が不当な契約から守られるための法律です。誤解や不十分な説明によって契約を結んでしまった場合に、一定の条件で契約を取り消したり、不当な条項を無効にできる仕組みを整えています。
ただし、フランチャイズ契約のように事業者同士が結ぶ契約には適用されないため、加盟を検討する際には「事業者としての自己責任」が強く求められます。契約前には専門家に相談するなど、十分な準備をして臨むことが大切です。
-
商号
商号とは、会社や法人の正式な名称のことを指します。たとえば「株式会社○○」「合同会社○○」などのように、会社の種類(株式会社・合同会社など)とともに記載されるのが一般的です。
この商号は、会社を設立する際に法務局へ登記され、税務申告、請求書の発行、契約書の記載など、法人としてのすべての取引や手続きにおいて使用される正式な名称となります。
商号の表記ルールと変遷
かつては、商号に使える文字に制限がありました。2002年10月31日までは商業登記規則により、商号にアルファベット(ローマ字)やアラビア数字、記号(例:&、@など)を使うことは認められていませんでした。
しかし、2002年11月1日から規則が改正され、以下のような表記も可能になりました。
- ローマ字(例:ABC、Tokyo)
- アラビア数字(例:123)
- 一部の記号(例:&(アンド)、・(中点)、’(アポストロフィ)など)
これにより、ブランディングや国際展開を見据えた柔軟な社名の設定ができるようになり、実際に英語表記を含む商号を採用する企業も増えています。
フランチャイズとの関連
フランチャイズにおいては、加盟者が法人として開業する場合、この「商号」で契約書を交わすことになります。本部との契約や税務処理、口座開設などすべての手続きは、商号で登録された正式な社名で行われるため、登記内容と書類記載を正確に一致させる必要があります。
また、フランチャイズ本部が許諾する店舗名やブランド名(=商標)とは異なるため、「商号」と「屋号・店舗名」の使い分けにも注意が必要です。
まとめ
商号は、法人としての「顔」となる正式な名称です。登記後はあらゆる取引・申請の場面で使用されるため、分かりやすく、信用を得やすい名前を選ぶことが大切です。
現在では、ローマ字や数字を使ったスタイリッシュな商号も可能となっており、企業のイメージ戦略の一環としても活用されています。 -
商圏
商圏とは、ある商業施設や店舗に来店が見込める顧客が居住・行動している地理的な範囲のことを指します。言い換えれば、「このお店にお客さんがどこから来るのか」を示すエリアです。
小売店、飲食店、商業施設、商店街など、立地型のビジネスにおいては非常に重要な分析要素で、店舗の売上や集客力に大きな影響を与えます。
一次商圏と二次商圏
商圏は一般的に、来店の頻度や利用率に応じて次のように区分されます。
- 一次商圏:店舗の主な顧客が居住している最も近いエリア。
来店客の約60〜70%を占めるとされ、日常的に通う人が多い範囲。 - 二次商圏:一次商圏の外側に位置するエリア。
来店客の15〜25%程度を占め、週末や特定の目的で来店する人が中心。
これらの商圏は、店舗を中心とした半径距離(例:1km圏、3km圏など)で表現されることが多く、都市部・郊外・地方といった周辺環境によって距離の目安が変わります。
商圏の広さは周辺環境で変わる
商圏の範囲は単純に距離だけでは決まりません。実際の来店行動には、以下のような周辺環境の要素が大きく関係します。
- 鉄道駅やバス停の有無
- 幹線道路や高速道路とのアクセス
- 競合店の有無や密度
- 住宅密集度やオフィス街の存在
- 駐車場の有無(車社会かどうか)
- 地形(川や山で分断されていないか)
たとえば、都市部では1km圏内でも十分な集客が見込めますが、地方や郊外では5km圏や車で15分圏内までを想定することもあります。
フランチャイズにおける商圏の活用
フランチャイズでは、出店候補地の選定や売上予測の根拠として商圏分析が必須です。加盟者に対しても、本部が指定する商圏調査資料やエリアマーケティング情報を提供するのが一般的です。
また、他の加盟店とエリアが重ならないよう、**商圏の重複防止(テリトリー保護)**の考え方を採用しているチェーンもあります。
まとめ
商圏は、店舗の集客力や売上に直結する非常に重要な要素です。一次商圏・二次商圏の区分をもとに、地域ごとの特性や顧客の行動パターンを理解することで、より効果的な立地選定や販促計画が立てられます。
フランチャイズ加盟を検討する際は、「どの範囲からお客様が来るのか」「そのエリアにどれくらいの需要があるのか」といった商圏分析の視点を持つことが、成功への第一歩になります。
- 一次商圏:店舗の主な顧客が居住している最も近いエリア。
-
ジャストインタイム
ジャストインタイムとは、必要なものを、必要なときに、必要な量だけ、適切な場所に届けることを目的とした流通・供給の仕組みです。トヨタの生産方式でも有名な考え方ですが、フランチャイズにおいても非常に重要な概念です。
具体的には、フランチャイズ加盟店からの商品注文に対して、本部や提携業者がタイミングを逃さず、正確に商品を供給する体制を指します。商品が早すぎても保管コストや廃棄リスクが増え、遅すぎれば販売機会を失うため、「ちょうどよく届く」ことが求められます。
なぜジャストインタイムが重要なのか?
この仕組みを整えることで、以下のようなメリットがあります。
- 在庫の最小化:必要以上に商品を抱える必要がなくなり、保管スペースやコストを削減できる
- ロスの削減:食品や消耗品などの廃棄ロスが減り、利益率が改善される
- 作業効率の向上:無駄な在庫整理や補充業務が減るため、現場スタッフの負担が軽減される
- 販売機会の最大化:品切れを防ぐことで、機会損失を減らせる
一見すると地味な分野に思われがちですが、店舗運営の効率化と利益改善に直結する非常に実務的かつ戦略的な要素です。
構築は簡単ではない
ジャストインタイムの仕組みを実現するには、本部・物流・加盟店の連携が欠かせません。たとえば、以下のような条件が求められます。
- 正確な売上・在庫データの把握
- 天候や季節変動などの需要予測力
- 柔軟かつ安定した配送システム
- 店舗ごとの注文タイミングや数量の適切な調整
こうした仕組みを整え、加盟店がストレスなく運営できる体制を構築することは、フランチャイズ本部の大きな競争力になります。
実際、ジャストインタイムを高度に運用できているフランチャイズは、「無駄が少ない」「利益が残りやすい」「業務がシンプル」といった理由で、加盟希望者からの評価も高くなります。
まとめ
ジャストインタイムは、フランチャイズビジネスのパッケージ価値を支える“縁の下の力持ち”のような存在です。物流や商品供給の質が高い本部ほど、加盟店の業務が効率化され、利益を残しやすくなります。
加盟を検討する際には、「本部はどのように商品を供給しているか」「配送の頻度や精度はどうか」といった点を確認することが、安定した運営につながる重要なポイントとなります。
-
社員独立制度
社員独立制度とは、フランチャイズ本部の社員が本部を退職し、自らフランチャイジー(加盟者)として独立・開業することを支援する制度です。これは、一定期間本部で働きながら現場での経験やノウハウを積み、準備が整った段階でフランチャイズ契約を締結し、事業主としてスタートする仕組みです。
制度の流れ
- 本部の社員として入社
- 給与を受け取りながら、店舗運営や経営の実務を経験
- 独立希望を表明し、所定の条件を満たす
- フランチャイズ契約を締結し、独立・開業
このように、実務経験を通じて段階的に独立の準備を進められるため、起業にありがちな「何から始めていいかわからない」「いきなり経営を担うのが不安」といった悩みを解消しやすい制度です。
社員側のメリット
- 経営未経験でも、給与をもらいながら実務を学べる
- 店舗運営の現場を理解したうえで独立できる
- 本部の支援体制やビジネスモデルをよく知った状態でスタートできる
- 開業までの準備が計画的に進められるため、リスクが抑えられる
独立に向けたサポート内容としては、資金調達のアドバイス、物件選定支援、研修、独立後の継続的なフォローなど、本部によって内容が異なります。
本部側のメリット
- 現場を熟知した即戦力がフランチャイジーになることで、店舗運営の安定度が高まる
- 新規加盟者の開拓に比べてミスマッチが少なく、スムーズな立ち上がりが期待できる
- 信頼関係がすでに構築されているため、本部と加盟者の間に強い連携が生まれやすい
- 独立希望者のキャリア支援として、採用面でも魅力的な制度になる
制度導入の背景
この制度は、もともと飲食業界やサービス業界で多く導入されており、「社員から独立したオーナーが成功しやすい」という実績が背景にあります。
長期間にわたり店舗での経験を積んだ社員が独立することで、ブランド理解度や現場感覚が高く、独立後も高い成果を上げやすいのが特徴です。まとめ
社員独立制度は、本部と社員の双方にとって大きなメリットがあるフランチャイズ独立支援の仕組みです。社員は現場経験を活かし、リスクを抑えて独立できる一方で、本部は信頼できるパートナーを加盟店として迎え入れることができます。
フランチャイズへの加盟を検討している方にとっても、「まずは社員として入社し、経験を積んだうえで独立を目指す」というキャリアパスは、非常に現実的で安心感のある選択肢です。
-
私募債
私募債とは、一般の投資家に広く募集するのではなく、特定の少人数の投資家に対して限定的に発行される社債(企業が発行する借入証書)のことです。法律上は、証券取引法(現在は金融商品取引法)における「募集(=公募)」には該当しない形式の資金調達手段です。
一般的に、50人未満の限られた投資家を対象に発行されるため、発行手続きが比較的簡素で、スピーディに資金調達ができる点が特徴です。
私募債の主な種類
私募債には、目的や発行対象に応じていくつかのタイプがありますが、大きく分けて以下の2つが代表的です。
1. 適格機関投資家向け私募債
証券会社、保険会社、銀行、投資ファンドなど、金融の専門知識を持つ機関投資家を対象に発行されるもの。大手企業や中堅企業が活用するケースが多く、信用力の高さが求められます。
2. 少人数私募債(縁故債)
主に中小企業や小規模事業者が、取引先・関係者・知人など信頼できる相手(縁故者)を対象に発行する私募債です。
一般的に1億円未満であれば、担保や保証が不要で、金融庁や都道府県への届出・報告義務も免除されるというメリットがあります。少人数私募債のメリット
特に中小企業にとっては、銀行融資以外の資金調達方法として、以下のような利点があります。
- 発行手続きが簡易でスピーディ
- 銀行借入と異なり、保証人や担保が不要な場合が多い
- 投資家との信頼関係を活かせる(融資より柔軟な条件で交渉可能)
- 利息や償還条件などを自由に設定できる
また、企業の将来性や事業計画を評価してもらえれば、信用情報に左右されずに調達できる可能性もあります。
注意点
私募債は制度としての柔軟性がある反面、**発行後の返済責任は明確に残るため、返済計画や資金使途をしっかり立てておく必要があります。**また、縁故者との関係を大切にしながら、適正な条件設定と丁寧な説明が求められます。
まとめ
私募債は、特定の投資家を対象にしたシンプルかつ柔軟な資金調達方法です。とくに中小企業やフランチャイズ事業の拡大を目指す経営者にとって、銀行融資に頼らない選択肢として注目されています。
少人数私募債は、発行手続きが簡易でコストも低く、信頼関係を前提とした資金調達ができる点が大きな魅力です。適切な活用により、資金の自由度を高め、事業の成長を後押しする手段として活用できます。
-
シフト表
シフト表とは、店舗で働く従業員の勤務日や勤務時間を管理するためのスケジュール表のことです。日ごと、週ごと、月ごとなどに区切って作成されるのが一般的で、アルバイトやパート、社員など全スタッフの勤務体制を一覧できるようになっています。
店舗のバックヤードや共有スペースに掲示されたり、最近ではスマートフォンアプリやクラウドサービスを使って共有されることも増えています。
シフト表の役割と重要性
シフト表は単なる勤務時間の記録表ではなく、店舗運営そのものを左右する「オペレーション設計の土台」でもあります。適切なシフト表があることで、次のようなメリットが生まれます。
- 混雑時間帯に人手が足りない、といったトラブルを防げる
- 業務ごとに適切な人員配置ができる
- 従業員の労働時間や休憩を正しく管理できる
- 無駄な人件費や過剰シフトを抑えられる
とくに飲食店や小売店など、時間帯ごとに来店客数が大きく変動する業種では、売上と人件費のバランスを最適化するための重要なツールとなります。
誰が作成するのか?
シフト表の作成は、基本的に店舗の責任者(店長・オーナー・リーダー)が担当します。従業員の希望やスキル、業務の繁閑、売上予測などを考慮しながら、「誰が、いつ、どのポジションで働くか」を組み立てていきます。
多くのフランチャイズ本部では、作成マニュアルや参考テンプレートを用意しており、新人店長でも一定のルールに沿って作成できるような仕組みが整っています。
シフト表から見える改善点
よくできたシフト表は、単なる勤務予定表にとどまらず、店舗運営の見直しや改善点の「気付き」を与えてくれる資料でもあります。
- 特定のスタッフに業務が偏っていないか
- 売上が低い時間帯に人件費をかけすぎていないか
- 退勤・出勤が連続しすぎていないか(過労防止)
- 教育が必要な新人にベテランをつけているか
こうした視点を持ちながらシフト表を作成・更新していくことで、「現場力」が強い店舗へと成長していきます。
まとめ
シフト表は、店舗経営の効率や従業員の働きやすさ、サービス品質を支える基本のツールです。フランチャイズ店舗においては、オペレーションの安定と利益管理の両方を担う役割を果たしています。
単なるスケジュール表としてではなく、人の動き=店舗の動きとして設計・分析する視点を持つことで、現場の生産性とチーム力は大きく向上します。
-
死に筋
死に筋(しにすじ)とは、店舗で陳列されている商品の中で、販売実績が低く、ほとんど売れないまま売り場を占拠してしまっている商品のことを指します。別名「不動在庫」や「低回転商品」とも呼ばれることがあります。
商品が売れ残り続けると、在庫が滞留するだけでなく、本来なら「売れる商品」を展開すべき売り場スペースを無駄にしてしまうため、店舗の売上や利益に悪影響を与えます。
なぜ「死に筋」が問題なのか?
死に筋の商品が売り場に残り続けることで、次のような機会損失が発生します。
- 売れ筋商品の展開スペースが不足する
- 新商品や季節商品の導入が遅れる
- 棚割り(商品の陳列計画)が崩れ、見た目が悪化する
- 回転率が落ち、在庫資金が寝てしまう
つまり、死に筋商品を放置することは、売場の鮮度を失い、利益を生まない商品にコスト(棚代・在庫管理・発注業務)をかけ続けることになります。
死に筋を見抜くには?
死に筋を早期に把握するためには、売上データや在庫データを定期的にチェックする習慣が必要です。
- 〇日間連続で売れていない
- 回転率が月1以下(=月に1個も売れない)
- 発注から●日経っても一定数量が残っている
- 近隣店舗と比べて売上が極端に低い
このような指標を設定し、定期的に棚卸し・商品分析を行うことが、死に筋の可視化につながります。
死に筋への対応策
死に筋商品を発見したら、次のような対応が一般的です。
- 値下げ(ディスカウント)による在庫一掃
- まとめ売り、特売、セールイベントへの活用
- ギフトやノベルティとの組み合わせ提案
- 時期や場所を変えて再展開(再販)
- 返品・廃棄・倉庫移動などで売り場から撤去
特にフランチャイズ店舗では、本部からの商品供給が多くなるため、死に筋の早期発見と対応は店舗ごとの裁量が問われる重要な業務になります。
まとめ
死に筋は、店舗の“利益を奪う沈黙の敵”です。放っておけば売り場の鮮度を落とし、売上のチャンスを逃すことになります。一方で、データに基づいて見直しを行い、柔軟に対応することで、売り場の最適化と利益改善につなげることができます。
シビアな在庫管理が求められる現場では、「売れない商品」を見極めて動かす力も、店舗運営に欠かせない重要なスキルです。
-
自主開示基準
自主開示基準とは、日本フランチャイズチェーン協会(JFA)が1999年に独自に定めた情報開示のルールです。目的は、フランチャイズ本部と加盟希望者との間における情報の非対称性を緩和し、より透明性の高いフランチャイズビジネスを実現することにあります。
法律の対象外もカバーする「自主的なルール」
日本には「中小小売商業振興法」によって、特定業種のフランチャイズに対し、事前の「法定開示書面」の交付が義務付けられています。しかし、すべてのフランチャイズ業種がこの法律の対象になるわけではありません。
このためJFAは、法律の適用外となる業種にも透明性を持たせるために、自主的な情報開示基準を定めたのです。JFAに加盟するすべての本部はこの基準を尊重し、加盟希望者への説明責任を果たすよう求められています。
開示される主な項目
「自主開示基準」で定められた情報は、法定開示書面(22項目)に加えて、さらに詳細なデータが含まれています。たとえば:
- 直営店・加盟店の別を明示した売上高・店舗数の5年間の推移
- 経常利益・税引後利益などの財務データ
- 本部の役員一覧
- フランチャイズ事業に関連する訴訟・トラブル履歴
- 加盟契約終了後の対応実績(契約解除件数など)
こうした情報を開示することで、本部の財務状況や拡大の実績、組織体制、健全性などを、加盟希望者が事前に把握しやすくなります。
加盟希望者への配布と提出義務
JFAでは、この自主開示基準に基づく資料(=自主開示書面)を、フランチャイズへの加盟を検討している希望者に事前に説明・配布することを推奨しています。さらに、JFAに加盟しているフランチャイズ本部は、この開示書面を協会(JFA)にも提出する義務があります。
加盟希望者にとっては、本部の信頼性や将来性を見極める重要な材料になるため、資料請求や面談の段階でこの書面の有無を確認することが非常に重要です。
まとめ
自主開示基準は、法律の枠組みを補う「フランチャイズ本部の信頼性を測る一つの基準」です。フランチャイズ加盟は中長期にわたるパートナーシップであり、事前の情報が不十分だとトラブルにつながりやすくなります。
しっかりとした本部であれば、この自主基準に基づく資料を用意し、透明性ある説明を行ってくれます。加盟を検討する際は、パンフレットや説明会の内容だけでなく、「自主開示書面」を活用して、本部の実態を冷静に見極める視点を持ちましょう。
-
事業用借地権
事業用借地権とは、店舗や事務所、倉庫などの「事業目的」で、地主から土地を一定期間借りることができる権利です。これは「定期借地権」の一種で、住居ではなく、商業的な用途のために設定される契約形態です。
2008年の法律改正により、10年以上50年未満の範囲内で契約することが認められ、現在ではフランチャイズ出店やロードサイド店舗の開業などで広く利用されています。
一般的な借地契約との違い
事業用借地権は、通常の借地契約と大きく異なる点がいくつかあります:
- 契約更新がない:満了時には契約終了となり、原則として再契約は行われません(自動更新されません)
- 建物の解体義務がある:契約満了後は、建てた建物(店舗・施設など)を解体し、更地にして地主へ返還しなければなりません
- 公正証書での契約が必要:口約束や私的な契約書ではなく、法的効力のある「公正証書」で契約を締結する必要があります
これにより、地主・借主の双方が安心して契約できる明確なルールが確保されています。
フランチャイズ出店との関係
フランチャイズやロードサイドビジネスでは、「土地は借りて、建物だけを自社で建てる」というケースが多く、その際にこの「事業用借地権」がよく活用されます。
とくに以下のような場合に適しています:
- 長期的に土地を使いたいが、購入するコストを抑えたい
- 出店リスクを下げつつ、好立地に進出したい
- 一定期間だけ事業展開したい(例:仮設店舗、期間限定業態など)
土地を買わずに出店できるため初期投資を抑えられ、契約終了後に柔軟に撤退・移転が可能な点も、中小企業や個人事業主にとって大きなメリットです。
借地料の設定
事業用借地権では、借地料(家賃)を収益性に応じて設定するケースもあります。たとえば、「売上や粗利益の何%」といった形で計算する場合もあり、単純な固定家賃よりも実情に即した柔軟な交渉が可能です。
注意点
事業用借地権を活用する際は、以下の点に注意が必要です:
- 期間満了時の撤退コスト(解体費用)をあらかじめ見積もっておく
- 契約内容の詳細(再契約可否・中途解約・原状回復条件など)を公正証書に明記する
- フランチャイズ本部と事業用借地契約の期間・更新方針が合っているか確認する
契約期間が決まっているからこそ、撤退計画も含めて戦略的に運用することが大切です。
まとめ
事業用借地権は、土地を購入せずに長期出店できる柔軟な手段として、多くの事業者に利用されています。契約期間や解体義務といった制約はありますが、初期投資を抑えつつ好立地に進出できるメリットは非常に大きく、特にフランチャイズ出店では定番の手法です。
安易に契約せず、専門家(不動産業者・行政書士・弁護士など)と相談しながら、「立地」と「契約条件」を総合的に見て判断することが、後悔しない出店への第一歩です。
-
サブリース
サブリースとは、フランチャイズ本部が物件(不動産)を一括で借り上げたうえで、それを加盟希望者に“又貸し”する仕組みのことです。つまり、本部が物件の借主となり、その物件を再び加盟者に貸し出すことで、店舗開発や出店をサポートします。
サブリースの特徴と目的
この仕組みは、資金力に乏しいが、運営力・マネジメント力に優れた加盟希望者を支援する目的で使われることが多く、フランチャイズチェーンの拡大戦略において重要な役割を果たします。
通常、フランチャイズ加盟においては、店舗の物件取得・契約・工事なども加盟者が自ら行う必要がありますが、サブリースの場合は、
- 本部が優良物件を確保
- 加盟者が初期費用を抑えて入居
- 店舗運営に専念できる環境を提供
という流れで、出店のハードルを下げる仕組みとなっています。
本部側のメリット
- 主導権を持って戦略的な立地に店舗展開できる
- 資金力に不安のある加盟希望者とも契約できる
- 店舗開発スピードを加速できる
- 物件の空室リスクを抑えつつ収益を得られる
加盟者側のメリット
- 賃貸物件の契約リスク(保証金・審査など)を回避できる
- 初期投資を抑えて出店可能
- 店舗物件の確保にかかる手間を軽減できる
- 本部の支援を受けながら運営に集中できる
ただし、家賃や契約条件は本部経由となるため、通常の賃貸契約よりも自由度が低くなる場合があります。
タンキー型フランチャイズとの関係
このサブリース方式は、いわゆる「タンキー型フランチャイズ(Turnkey Franchise)」に該当します。
タンキーとは「すぐに鍵を回せば営業できる」状態を意味し、本部が物件探し、内外装工事、設備導入、契約などすべてを整えた状態で加盟者に引き渡すモデルです。加盟者は運営に専念できる一方で、初期費用や契約内容、利益配分などについて、本部の設計に従う形になるため、リターンとリスクのバランスをよく理解して契約することが重要です。
注意点と確認事項
サブリース契約を検討する際には、以下のような点を事前に確認しておく必要があります:
- 家賃の金額と算出根拠(固定or変動)
- 契約期間と途中解約時の条件
- 原状回復の範囲や責任の所在
- 売上が悪化した際の家賃交渉の可否
- 本部が物件を一括借上している理由
サブリースは、加盟者の負担を軽減しつつ出店を後押しする仕組みですが、契約条件が不明確な場合にはトラブルの原因にもなり得ます。
まとめ
サブリースは、本部が用意した物件を加盟者に貸し出し、出店の障壁を下げる柔軟なフランチャイズ支援策です。
資金力に不安のある起業希望者や未経験者にとって魅力的な制度であり、店舗運営のみに集中できる環境が整えられる一方、契約の自由度は通常よりも制限されることを理解しておく必要があります。契約前には、家賃、期間、更新、解約条件などを丁寧に確認し、本部との信頼関係のもとで納得したうえで加盟判断を行いましょう。
-
サブ・フランチャイズ・システム
サブ・フランチャイズ・システムとは、フランチャイズ展開において、本部(マスターフランチャイザー)から地域単位などの運営権を与えられた“中間的な立場の組織”が、代わりにフランチャイジー(加盟者)を開発・指導する仕組みのことを指します。
このシステムにおいて結ばれる契約を「サブ・フランチャイズ契約」と呼び、その全体的な構造や体制を“システム”として表現しています。どのような仕組みか?
通常、フランチャイズビジネスでは、本部が直接すべての加盟者に対して契約・指導・支援を行います。
しかし出店エリアが全国に広がると、本部がすべての加盟店を管理・運営するのは物理的にも負担が大きくなります。このとき、本部は一部の地域について「サブ・フランチャイズ権」を委ねることで、以下のような役割を地域単位で分担します:
- 加盟店の募集・契約(本部ではなくサブFCが行う)
- 出店支援・物件調査
- 研修・教育・運営指導(SV業務)
- 売上・KPIの管理
- 本部とのパイプ役としての調整
本部 → サブ・フランチャイザー → 加盟店(フランチャイジー)
という3層構造になります。サブ・フランチャイズ・システムのメリット
本部(マスターフランチャイザー)の立場から:
- 全国展開をスピーディに進められる
- 地域特性に合った店舗運営が可能
- 現場支援を地域に任せられることで本部は企画や開発に集中できる
サブ・フランチャイザーの立場から:
- 地域内で独自にFC展開できるビジネス権利を獲得
- 店舗運営+SV指導・営業ノウハウを活かせる
- 収益の一部をロイヤルティとして受け取れる
加盟店の立場から:
- 地域に精通したサポート担当者(サブFC)から密な指導を受けられる
- ローカルな事情に合った柔軟な運営サポートが得られる
よくある業種や事例
- 教育業界(学習塾・英会話教室)
- 介護・訪問サービス事業
- 清掃・ハウスクリーニング系
- 地方でのロードサイド型飲食店
地方エリアの開発力・支援体制を強化する必要がある業種で導入されることが多く、「ローカルでの拠点展開 × 本部ブランド」の掛け合わせが成長の鍵となります。
注意点とリスク
- サブ・フランチャイザーの支援力・教育力によって加盟店の成功率が大きく左右される
- ブランドイメージやサービスの一貫性が地域によってばらつくリスクがある
- ロイヤルティ配分やサポート内容など、契約内容を明確に定義する必要がある
まとめ
サブ・フランチャイズ・システムは、本部の運営力を地域に分散し、より効率的・戦略的にフランチャイズ展開を広げるための仕組みです。
地域密着型の支援体制が強化されることで、加盟店にとっても安心して事業を始めやすくなる反面、サブ・フランチャイザーの質や体制によって成功可否が分かれる側面もあります。フランチャイズに加盟する際や地域展開を検討する際は、このサブ・フランチャイズ体制の有無とその運営状況を確認することも、重要な比較ポイントとなります。
-
サブ・フランチャイズ(エリアフランチャイズ制)
サブ・フランチャイズとは、フランチャイズ本部(マスターフランチャイザー)が、ある地域(エリア)に限定してフランチャイズ権を他の事業者に譲渡する仕組みのことです。
この制度は「エリアフランチャイズ制」とも呼ばれ、広域展開を効率的に進めるために使われる代表的な手法です。譲渡された事業者は「サブ・フランチャイザー」となり、本部の代わりにそのエリア内でのフランチャイズ展開を担当します。
仕組みの概要
フランチャイズ本部は、以下のような契約をサブ・フランチャイザーと結びます:
- 特定地域(例:関西エリア、○○県など)におけるフランチャイズ展開権を付与
- 加盟店開発・契約・営業指導の一部またはすべてを委ねる
- サブ・フランチャイザーから対価(契約金やロイヤルティの一部)を受け取る
これにより、本部は全国展開の手間を軽減しながら、地域密着型の事業拡大が可能となります。
サブ・フランチャイザーの役割
サブ・フランチャイザーには、以下のような「本部に近い機能」が与えられます(一部制限あり):
- 自エリア内でのフランチャイズ加盟希望者の募集・契約交渉
- 加盟店に対する出店支援、研修、SV業務などの営業サポート
- 加盟金・ロイヤルティの徴収(全額または一部)
- 地域戦略の立案・売上管理・トラブル対応
サブ・フランチャイザー自身が直営店舗を持つケースも多く、そのエリア内でリーダー的役割を果たします。
導入のメリット
フランチャイズ本部にとって:
- 地域ごとの開発・指導業務を分担できる
- 地域特性に応じた柔軟な展開が可能
- スピード感をもって多店舗化を図れる
サブ・フランチャイザーにとって:
- 独立したエリア運営権を得て、自らの裁量で事業を展開できる
- ロイヤルティ収入などの継続収益を得られる
- 地域のネットワークや不動産情報を活かせる
加盟希望者にとって:
- 地元に精通した担当者(サブ・フランチャイザー)から密な支援を受けられる
- 出店相談からオープン後のフォローまでの対応がスムーズ
注意点とリスク
サブ・フランチャイズ制には多くのメリットがありますが、以下のような注意点も存在します:
- 本部とサブ・フランチャイザーの間でブランドや方針の統一が必要
- エリア間でサービスや指導内容のばらつきが出るリスク
- 加盟者にとって「本部なのかサブFCなのか」が曖昧になるケースがある
- 責任範囲(契約権限・収益分配など)を明確に契約書に定める必要がある
特に、トラブルやクレーム発生時に「どこが対応するのか」が不明瞭な場合、信頼低下や運営トラブルの原因になりかねません。
まとめ
サブ・フランチャイズ(エリアフランチャイズ制)は、広域なフランチャイズ展開において、地域の事業者と協力しながら効率的に成長するための有効な戦略です。
本部とサブ・フランチャイザーの間で権限と責任を適切に分担し、地域特性に合わせた運営を行うことで、加盟者へのサポート体制もより充実します。
加盟を検討する際は、自分の出店予定地域が「本部直轄か、サブFCが担当か」を確認し、契約相手・支援体制の違いを理解したうえで判断することが重要です。
-
サブ・フランチャイザー(エリアフランチャイザー)
サブ・フランチャイザーとは、フランチャイズ本部(マスターフランチャイザー)から一定の地域(エリア)におけるフランチャイズ展開の権限を譲り受けた中間的な役割を担う事業者です。
「エリアフランチャイザー」とも呼ばれ、主に地域密着型でのフランチャイズ拡大を目的に設置されるポジションです。どのような立場か?
サブ・フランチャイザーは、フランチャイズ本部との契約によって、次のような業務や権利をそのエリア内で行うことが許されます:
- 加盟希望者とのフランチャイズ契約の締結や交渉
- 加盟店の開発(出店サポート)と運営支援(SV業務)
- ロイヤルティや加盟金の一部徴収
- 地域でのプロモーション・販促企画の実施
簡単に言えば、「エリア限定の小さな本部」のような存在です。
フランチャイズ本部との役割分担
サブ・フランチャイザーが地域内の加盟開発・運営を担当する一方で、以下のような重要な経営資源や企画・商品管理などは、本部が引き続き担います:
- ブランドの商標権や使用許諾
- 商品・サービスの提供と管理
- 店舗システム・マニュアルの設計
- メニューや販促の大方針
- 法令順守・品質基準の統一
つまり、「戦略・ブランド管理は本部」「地域での実務・運営はサブFC」という形で、役割が明確に分かれているのが特徴です。
どんな企業がサブ・フランチャイザーになるのか?
一般的に、サブ・フランチャイザーは以下のような事業者が多いです:
- 自社でフランチャイズ店舗を複数展開してきた企業
- 地元の不動産ネットワークや人材に強みを持つ法人
- 本部と信頼関係を築き、長年実績を積んだ有力加盟店
彼らはその地域に詳しく、独自のネットワークや運営力を活かして新規加盟者を開拓・育成する役割を担います。
加盟希望者にとっての意味
加盟希望者から見たとき、サブ・フランチャイザーが担当エリアに存在する場合:
- 相談窓口が本部ではなく地域の事業者になる
- 研修や開業支援、店舗運営の指導をサブFCから受ける
- サポートのスピードや密度が高まりやすい
一方で、エリアによって運営スタイルや対応にばらつきが出る可能性もあるため、誰が実質的に支援してくれるのかをよく確認してから契約を進めることが大切です。
まとめ
サブ・フランチャイザー(エリアフランチャイザー)は、フランチャイズ本部から地域展開の権限を託された重要な存在です。
本部のノウハウやブランドを活かしながら、エリアごとに柔軟かつスピーディなフランチャイズ展開を実現できる仕組みとなっています。加盟検討者にとっては、どの地域に誰が支援してくれるのかを知ることが、安心して事業を始める第一歩になります。
-
サービス・マーク
サービス・マークとは、フランチャイズなどの「サービスを提供する事業者」が自社のサービスを識別するために使用するマークやロゴなどの標章のことです。
これは、商品に対する「商標」に対して、無形の“サービス”に対する識別標章として扱われます。法律上の位置づけ
日本では、平成3年(1991年)の商標法改正により、「役務商標(えきむしょうひょう)」としてのサービス・マークの登録制度が正式に整備されました。
これにより、たとえば以下のような事業分野でサービス・マークが法的に保護されるようになりました:
- 飲食店、カフェ、理美容、エステなどの接客サービス業
- 教育サービス(学習塾、英会話スクールなど)
- 配送、修理、介護、保育、クリーニングなどの生活支援サービス
それまでは「物の商標」しか登録できなかったため、サービス業のブランド保護に大きな前進となりました。
サービス・マークの役割
- サービス提供者の識別
→ どの企業や店舗が提供するサービスなのかを明確にします。看板や広告に表示されるマークがその役割を果たします。 - サービスの品質保証
→ 継続的にサービスに付けて使用することで、「このマークがついているサービスなら安心」という消費者の信頼形成にもつながります。 - ブランド価値の保護
→ サービス・マークが商標登録されていれば、模倣や不正使用を法的に差し止めることができ、ブランド価値を守ることができます。
フランチャイズにおける重要性
フランチャイズビジネスでは、「同じブランドで全国にサービスを提供する」ことが最大の強みです。
そのため、本部が商標権(サービス・マークを含む)を保有し、加盟店に対してその使用権を許諾することで、ブランドの統一性と信頼性を担保しています。具体的には:
- ロゴマーク、店舗名、キャッチコピー、看板のデザイン
- ユニフォームや包装資材に使われるシンボルマーク
- サービスマニュアルに準拠した接客スタイル
などが、サービス・マークに基づいて設計されます。
注意点
サービス・マークを使用するには、以下のような点に留意が必要です:
- 本部が商標登録しているマークかどうかを確認する
- 使用権の範囲(期間、地域、媒体など)を契約で明確にする
- 本部の許可なくロゴや表記を改変しない
- 不正使用によってブランドの信頼を損なわないよう徹底管理する
加盟店にとっては、ブランドの信用力を借りて営業できる一方、ブランドルールに従った運営が求められることになります。
まとめ
サービス・マークは、フランチャイズやサービス業における「見えない価値(ブランド)」を、見える形で保護・管理するための重要な制度です。
単なるロゴではなく、信頼・品質・一貫性を象徴するマークとして、事業の成長に直結する資産です。フランチャイズ加盟時には、このマークがどのように登録され、どう使えるのか、商標契約の内容をしっかり確認することが大切です。
-
再販売価格維持(再販制度)
再販売価格維持(再販制度)とは、メーカーや製造業者が、小売店や販売業者に対して商品の販売価格(特に最低価格や定価)を指定し、値引き販売などを制限する制度のことを指します。
これは簡単に言えば、「この商品は絶対に◯円で売ってください」とメーカーが小売側に強制する仕組みです。通常、市場での価格は販売側が自由に決められるべきですが、この制度がある場合、小売店はメーカーの指定価格で販売しなければならず、値引きが禁止されます。
日本における法的位置づけ
独占禁止法第19条および公正取引委員会の「不公正な取引方法」第12号により、販売価格の拘束(再販価格維持)は原則として禁止されています。
これは、自由な価格競争を妨げ、市場の健全な競争を阻害する恐れがあるためです。ただし、例外的に次の6品目については再販制度が認められています(2025年8月現在):
- 書籍
- 雑誌
- 新聞
- 音楽用CD
- 映画のDVD・Blu-ray
- ゲームソフト(著作物として扱われるもの)
これらは主に「著作物」であり、価格競争によってコンテンツ産業が衰退するのを防ぐ目的で、再販価格維持が例外的に許されています。
海外との違い
アメリカなど多くの国では、再販制度は存在せず、すべての小売業者が自由に価格設定を行います。
たとえば、書籍や電子書籍のセール、クーポン適用、バンドル販売などが一般的で、日本よりも価格競争が活発です。フランチャイズにおける取り扱い
フランチャイズ契約のもとでは、本部(フランチャイザー)は加盟店(フランチャイジー)に対し、ブランド名(商標・商号)の使用許諾や商品・サービスの供給を行い、チェーン全体での品質や価格帯の統一を図ることが前提とされます。
このため、以下のようなケースは実務上よく見られます:
- 本部が「推奨販売価格」や「標準価格表」を提示
- メニューやパッケージ価格がチェーン全体で統一されている
- 販促キャンペーンの実施価格が本部主導で決定される
こうした「価格のガイドライン」は、あくまで“推奨”の範囲であれば問題ありません。
しかし、以下のような行為は独占禁止法違反となる可能性が高く、注意が必要です:
- 本部が加盟店に対し、値引き販売やセールを禁止する
- 一方的に販売価格の拘束を行い、違反した加盟店にペナルティを課す
- 地域の需要に応じた価格調整を一切認めない
これらは「再販売価格の拘束」に該当し、独占禁止法第2条第9項第4号で禁止されています。
地域事情と裁量
たとえば、都市部と地方で客層や購買力が異なる場合、同じ商品でも価格を柔軟に調整する必要があります。
また、売れ行きが悪い商品や在庫処分を目的とした値引きは、加盟店の運営上必要な判断であり、本部が一律に制限することはできません。そのため、フランチャイズ契約の中では「価格設定に関するルール」を明文化し、加盟店の裁量をどこまで認めるかが重要になります。
まとめ
再販売価格維持(再販制度)は、本来は禁止されている価格拘束行為であり、フランチャイズ本部であっても、加盟店に対して一方的に価格を強制することはできません。
ただし、チェーンのブランド価値や顧客体験を守る観点から、「価格の統一感」は重要な戦略の一部でもあります。
このバランスをとるためにも、以下を意識して運営・加盟検討を行いましょう:地域や業態による価格調整の可否を本部と共有する
推奨価格と拘束価格の違いを理解する
契約書における価格設定の裁量範囲を確認する
-
最低保証制度
最低保証制度とは、フランチャイズ加盟店の売上状況にかかわらず、本部が定めた一定の収入額を下回った場合に、その差額を本部が補填する仕組みのことです。
主にコンビニエンスストア業界で導入されており、加盟者の収入を一定水準で保証する制度として知られています。仕組みの概要
通常、フランチャイズでは以下のような流れで利益が分配されます:
- 加盟店が商品を販売し、売上を得る
- 売上から仕入原価を差し引いた「売上総利益(粗利)」が算出される
- そこからフランチャイズ本部へロイヤリティ(運営費)を支払う
- 残った金額が加盟店の手元に残る利益となる
しかし、売上が少ない月には、加盟者の利益が極端に減ってしまうこともあります。
こうした場合に、加盟店の利益が本部が定めた「最低保証額」に満たないとき、その差額を本部が補てんするのが、この「最低保証制度」です。導入の背景
特に24時間営業・年中無休で運営されるコンビニエンスストア業態では、売上に季節変動や立地条件の影響が大きく、開業初期や地域によって安定収益が難しいことがあります。
そのため、最低保証制度は以下のような加盟者保護策として導入されています:
- 「売上が伸びないと生活できない」という不安の軽減
- 加盟希望者の参入障壁を下げる
- 安定収入があることで長期的な事業継続が可能になる
加盟者にとってのメリット
- 収入の最低ラインが確保されているため、安心して経営に専念できる
- 不安定な売上でも生活資金が確保できる
- 開業初期の立ち上がり時期でも経済的に大きなリスクを回避できる
特に、フランチャイズが初めての人や、資金に余裕がない状態での独立開業を考えている人にとっては、非常に心強い制度といえます。
一方のデメリット・注意点
ただし、以下のような側面からデメリットと感じる人もいます:
- 目標収入が保証されることで「最低ラインを超えれば良い」と消極的な経営になる可能性がある
- 努力しても、努力しなくても保証額が同じという心理的な甘えが生まれやすい
- 独立開業の本来の目的である「自己裁量で稼ぐ楽しさ」や「経営の達成感」が薄れることがある
- 保証額がある分、本部からの業務管理や営業ルールが厳しくなるケースもある
また、本制度を「フランチャイズ経営の自主性を損ねる」として採用していない本部も多数存在します。
特に飲食やサービス業など、オーナーの創意工夫が結果に直結する業種では、導入が少ない傾向にあります。加盟前に確認すべきポイント
最低保証制度があるかどうかは、フランチャイズ本部ごとに異なります。加盟前には必ず以下の点を確認しましょう:
- 保証対象となる金額(月額◯円など)
- 保証期間(開業から◯ヶ月または1年など)
- 対象となる条件(営業時間、従業員数、指定立地など)
- 補填方式(差額支給 or 実質的な割引など)
本制度の有無は、収支計画や生活設計に大きく影響する要素のため、契約前にしっかりと内容を把握することが重要です。
まとめ
最低保証制度は、売上が安定しない初期フェーズや厳しい立地条件でも、加盟者が一定の収入を確保できるように設けられた保護制度です。
一方で、自律的な経営意欲とのバランスや、制度による依存心の増加といった課題もあるため、制度の有無だけでなく、その設計内容まで丁寧に確認することが求められます。
丁寧にヒアリング
厳選したFCをご提案
専門コンサルタントが、お話をお伺いして
あなたに最適なフランチャイズを無料アドバイスします。
丁寧にヒアリング
厳選したFCをご提案
専門コンサルタントが、お話をお伺いして
あなたに最適なフランチャイズを無料アドバイスします。