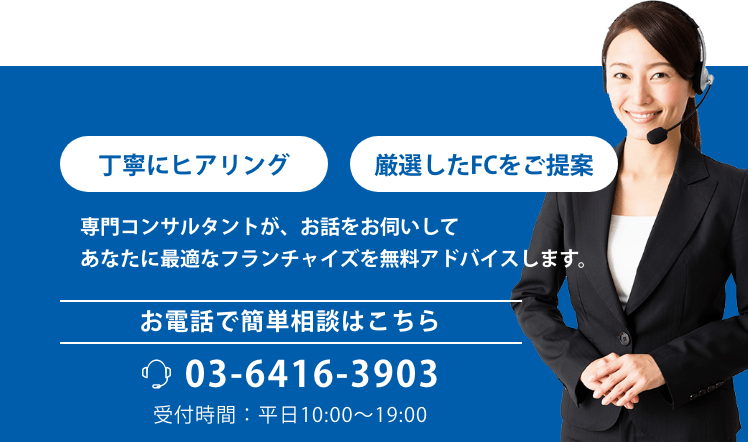フランチャイズ企業のススメ
-

3.フランチャイズで起業を目指す業種・業態を決める
自分のやりたいことがあるからという理由でフランチャイズ起業をするということが一般ですが、起業はしたいけど業種、業態は決めていないという方もいると思います。 いずれにしても、大切なのは情報収集です。世の中ではどういった変化が起こっているのか、これからどんな需要が増えるのか、どういったサービスを提供するのが良いのか…など、現在から数年後の未来、更にその先を見据えたうえで決めていきましょう。 代表的な業界をご紹介します。 小売業界 小売りと言えばコンビニやスーパーをイメージするのではないでしょうか。粗利益率はそこまで高くありませんが、ブランドと商品ノウハウにより本部の恩恵を十分に受けることのできる業種です。 飲食業界 粗利益率が高く人気の多い飲食業界。起業する人が多いため、競争が激しい業界です。 また、環境の変化を受けやすい業界で、常に社会の情勢や周辺環境にアンテナを張りながら運用していくことが大切です。 設備の準備にも費用が掛かる為、初期費用が他業界に比べ多くかかる傾向にあります。 サービス業界 こちらも粗利益率は高く、人気のある業界です。 マネージメントが難しく、事業を安定するまでに長期間かかる為、芽が出る前に諦めてしまうケースが多くあります。 しかし、起業する上での初期投資はそこまで高くなく、スタートさせやすいため、近年この業界で起業する人は増加傾向です。 上記3つの業界の中で、最近注目されている業種をご紹介します。 買取業界(小売) コンビニ業界ほどの規模ではないですが、規模としては2019-2020年では6000億円ほどでこれから規模拡大が期待されています。 AIやITツールを使った鑑定システムを買取業界では積極的に導入しており、鑑定経験のない人でも始めることが可能です。 介護業界(サービス) 2025年には国民の20%が高齢者になると言われており、今後需要が期待できる業界です。また、社会問題への貢献という部分もあるので非常にやりがいのある魅力的な業界です。設備投資として、車両費、人件費、機材など準備するものが多く、開業資金は多少必要ではありますが、全国を拠点対象とで、開業しやすいです。 学習塾業界 電車や駅のポスター、テレビCMなど最近よく目にする学習塾の宣伝。こういった広告を目にするのは、実は少子化の傾向にもかかわらず、世の中の一人当たりにかける勉学等の費用は増加しているためです。 学習塾の経営は自ら子供に教える必要はないので、授業をするスキルは必要ありません。 フランチャイズで起業すればすでに教師、生徒、教室全てがそろった状態で引継ぎ、スタートすることも可能なので、起業リスクを抑えることも可能です。 ハウスクリーニング業界 「お掃除の技術」さえあれば開業資金が無くてもスタートすることのできる業種です。店舗を構える必要もありません。 現在高齢化や共働き家庭が増えてきており、日常生活のサポートサービスは一般的なサービスとして認知され始めています。フランチャイズなので、掃除のノウハウはしっかりと学んでからスタートをすることが出来きます。 体を動かす仕事なので、体力的な面で不安があるかと思う方もいるかと思いますが、マンションなどの共有スペースの清掃といったような仕事も多いため、そこまで肉体労働なお仕事ではないので安心してください。 美容・リラクゼーション業界 アロマセラピー、整体、美容マッサージなど様々な業態のある業界です。経済産業省により2016年に「セラピスト」という職業が認定され、ますます人気が増加しています。 一部資格取得を必要とする業態もありますが、商業施設内で開業することもできるため、館の集客の恩恵を受けながら運営することが出来ます。 リペアビジネス業界 どちらかというとまだマイナー業界ではありますが、現代の人たちは環境への意識が高まっていることから、ニーズの多い業界です。 家具や車などの修理のノウハウを身に着けることが出来るので、ご自身の知識を活かしながら長く仕事を続けることが出来るのもメリットの一つです。 こういった業界のように、すでに成功している業界は「なぜ成功しているのだろう?」「どういったところに需要があるのだろう?」と要因を手繰ることでたどり着く答えを基に業界、業種を決定するのも一つの方法です。
-

4.良いフランチャイズの見分け方(フランチャイズ本部の情報収集)
良い本部と出会う フランチャイズで起業する場合、最大のメリットはフランチャイズ本部のノウハウを色々と提供してもらいながら事業を成功させることができると言うことです。 せっかく起業しても、フランチャイズの看板だけで何のフォローアップも受けられないのであればフランチャイズとして起業した意味がありません。 以下のポイントを抑えて自分にあったフランチャイズ本部を探してみましょう。 フランチャイズ本部の経営姿勢がわかる情報 本部の経営理念や事業に対する姿勢に共感できるかを確かめましょう。以下の4つのポイント抑えておきましょう。 フランチャイズチェーンの方針経営者の考え方企業の将来性組織風土や外部からの信頼、評判 フランチャイズを選ぶ上での必要情報 現状のフランチャイズの実情がわかる情報や、契約内容などフランチャイズを選択する上で判断材料となる情報が開示されているかを確認してください。 フランチャイズの契約内容資本金、店舗数、直営点比率、従業員数など起業スケールのわかる情報操業年月、沿革などの会社情報出退店舗数 フランチャイズ本部の持つ商品力と店舗展開力 フランチャイズ本部の持つ商品の開発力、独自性、商品供給の安定性、店舗のモデルや他店舗展開しているオーナーなどを確認しましょう。本部の持つ実力を確認します。 魅力的な商品展開商品供給の安定性商品の開発力モデル店舗の有無複数出店オーナーがどれくらいいるか 加盟店舗へのフォローアップについて フランチャイズとして加盟した際に、本部がどれくらいフォローしてくれるかを確認しましょう。具体的には以下のポイントを押させておきましょう。 開店するまでの開業前のサポート研修制度の充実経営に関する情報提供やアドバイス本部実施イベントにおけるFC店舗の参加の有無経営不振になった際のバックアップについて 店舗運営におけるコスト FC加盟することで実際に成功する可能性がどれくらいなのか、ランニングにかかるコストはいくらか、初期に必要な金額はどれくらいかなど確認しましょう。 利益率、損益ロイヤリティ、本部徴収額初期投資額とその回収目安 法定開示書面では、過去3年分の情報が公開されています(法定財務諸表)。 この書面は大変難しい内容になっており、専門家ですら難解で情報を集めるのに苦労することがあります。 以下に見るべきポイントをご紹介します。 フランチャイズ本部の安定性 流動比率 (流動資産÷流動負債×100%) 賃借対象表の流動資産と流動負債の比率を現したものです。会社の短期的な支払い能力を測ることができます。 流動資産とは現金預金、受取手形、売掛金、棚卸資産など、1年以内に現金化できる資産を指します。 流動負債とは買掛金、未払金、借入金など借入期間が1年以内の短期借入金などが該当します。 自己資本比率 (純資産÷総資産×100%) 自己資本率が高いほど安定した優良企業と言われます。 この比率が低いと、借入などの負債が多いと言うことになり、返済義務のあるお金が多く、中長期的に見ると倒産する可能性があると考えられます。 しかし、設備投資などにより一時的に変動しているフランチャイズ本部もあるため、どういった経緯で釈乳が多くなっているかを見てきちんと判断する必要があります。 収益性 売上高 利益率 (利益÷売上高×100%) その本部が実際にどれくらい稼ぐ力を持っているかを確認することができます。 ざっくりと確認するには上記の計算式のように売り上げに対する利益率を確認しておきましょう。 総資産利益率(ROA) (利益÷総資産×100%) 会社が持っている総資産に対する利益の割合です。本部が資産を有効的に活用して利益を生み出せているかを確認することができます。 成長性 前年比成長率 { (当期-前期)÷前期×100%} 前年に対してどれくらい売り上げが伸びているかを確認します。上記の計算式では前期と当期の比率ですが、前期と前々期も確認することで、継続的に成長しているかを確認することができます。 法定開示書面は中小小売商業振興法により、小売業、外食業は開示をする義務を負っているため、過去3年間のデータを見ることが出来ます。 また、近年、上記業界以外のフランチャイズ本部も法定開示書面を持つようになってきています。 この書面自体はとても難しい内容となっていますが、過去3年間の業績を見られるか見られないかで将来的なそのフランチャイズの将来性を大まかにみることが出来ます。
-

5.フランチャイズ本部を実際に見てみる(本部へのヒアリングリスト)
フランチャイズ本部訪問 情報収集はもちろんですが、実際にフランチャイズ本部で働いている人たちと会うことで、どう言った本部なのか、社風が自分自身にあっているかなど、ダイレクトに感じることができると思います。 訪問を承諾してくれる場合は、フランチャイズ本部としても、受け入れるに値する人物かかどうか判断する機会にもなるので注意しましょう。 必ず事前の準備を行ない、最低限の知識は持ってから訪問しましょう。 基本的には、話を聞かせてくれる担当の方の人柄や対応をしっかりとチェックしましょう。また、オフィスの清潔感や、社員の方の対応など社内の雰囲気など、基本的な会社としての基本的な部分も観察し、フランチャイズ本部が自分と合いそうかどうか検討しましょう。 時間も30分~1時間と限られた時間の中で質問が全て聞けないこともあります。 まずは重要なフランチャイズ本部へ徴収される費用に関して質問し、全て説明を受けるようにすることをオススメします。 (具体的な確認項目は後述します) 次に、現場の生の声を聞くために実際の加盟店を紹介してもらい、現地視察できるよう段取りを組んでもらいましょう。本部を通してアポを取ってもらう方が、直接アポを取るよりもスムーズです。 その他、書面ではわかりづらい部分や、詳しく知りたい箇所を質問し、自分自身不安や疑問に感じている部分を明確にしましょう。 加盟店訪問 本部を訪問した後に訪問することをお勧めします。現場と本部では意見が違う場合もあるので、現場の実際の意見を聞いてみましょう。できれば1店舗だけでなく、複数店舗訪問することで大体の現場の意見がわかると思います。 本部から紹介してもらった店舗以外にも訪れてみてください。様々な店舗からヒアリングをすることで、実際に自分が加盟した際に何が必要か、どう言ったことを考えていくべきかなど、成功するためのヒントを見つけることができます。 先ほど述べたフランチャイズ本部へ確認するべき費用について記載します。 大きく分けて「本部へ支払う費用」と「フランチャイズ本部以外へ支払う費用」の2つに分かれます。 これらを参照に本部へヒアリングしてみてください。 本部への支払い 加盟金 FCに加盟する際に支払うお金です。 保証金 これは加盟者が本部に契約する際に支払う預け金のことです。ロイヤリティや商品仕入れ責務などが果たせなかった場合に担保するために使用されます。何か未払いなどが発生した場合にはここから差し引かれますが、そう言ったことが特になければ、契約終了とともに基本的には全額戻ってきます。 ロイヤリティ 加盟後に毎月本部に支払うお金です。 フランチャイズと言うシステムを利用するためのシステム料金と考えると良いかもしれません。この算出方法は様々ですが、売り上げの10%だったり、月々固定額だったりとフランチャイズ本部によって様々です。 この金額が高いから、安いからと言う理由で選ぶよりは、受けることのできる恩恵に対して妥当かどうかを判断するようにしましょう。 設備投資費用 店舗を構える上で、オープンまでにかかる店舗準備費用です。外装、内装は本部の指示に従って準備、実際の支払いは直接業者にするなど、様々なので事前に確認しておくようにしましょう。 研修費用、販促、商品仕入れなどその他の費用 上記以外にも仕入れを始め、販促物、研修など、様々な費用が発生します。FCに加盟することで、何がどれくらいかかるのか、疑問点や不明点は事前に確認しておきましょう。 フランチャイズ本部以外で発生する費用 敷金(店舗保証金) 物件を契約する際に事前に貸主に預ける補償金です。家賃の未払いなどが発生した時にこの預かり金が当てられることがあります。また、店舗を手放す際にはクリーニングなどでこの費用が当てられることがあります。差額分は返金されますが、契約によっては無条件で敷金のX%が徴収されるケースもあります。 礼金、仲介手数料 礼金は貸主へ支払うお礼金です。こちらは返金されません。 仲介手数料は不動産を紹介してくれた不動産会社に支払う紹介手数料です。 前払い家賃 家賃は開店前の内装工事の段階から発生します。初期費用にかかってくる部分になるので、開店までにどれくらいの準備期間が必要か確認しておく必要があります。 求人広告費 費用としては大きくはないですが、定期的に募集をかけることもあるので確認しておきましょう。 株式会社などとして運営する場合は会社設立費用が必要です。会社の登記手続きは自分自身で行うか、司法書士に依頼して行うかで変わってきますが、10〜30万円程度かかります。 運転資金、生活資金 運転資金とは、店舗運営にかかる仕入れや人件費、家賃など最低限かかる1ヶ月間のコストです。また、経営不振になってしまった場合の生活するための資金も準備しておきましょう。 実店舗に訪問した際は実務的な部分や、FC本部からのフォロー面、オーナーが実際に感じているメリット、デメリットなど質問してみましょう。 また、いい面だけではなく、失敗談や、売り上げが伸び悩み厳しかった時期の話、またどのようにして乗り越えたのかなど、そういった話も聞いてみましょう。自分がそういった状況に直面した際の対策のヒントを得られるかもしれません。
-

6.法定開示書面
法定開示書面とは中小小売商業振興法によって定められている、フランチャイズの事業概要などを加盟希望者に対して事前に開示する書面のことです。 内容としてはフランチャイズ契約書の内容を加盟者に対してわかり易くしたものになっています。 特定の業種(小売、飲食のフランチャイズチェーン)においてはこれが義務付けられており、フランチャイズ加盟を検討している方に対して事業概要や契約内容、その他の情報を書面によって事前に開示して説明する義務があります。情報開示書面という事もあります。 現在では独占禁止法のガイドラインの観点から、上記の特定業種以外でも開示書面を持ち、加盟希望店に説明するフランチャイズ本部が一般的となってきています。 平成14年4月に追加・拡充された後、現在開示すべき項目は合計22項目となりました。 開示項目一覧 本部事業者の名称・住所・従業員数・役員の役職名及び氏名本部事業者の資本金・主要株主・他の事業の種類子会社の名称及び事業の種類本部事業者の直近3事業年度の賃借対照表及び損益計算書FC事業の開始時期直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移直近の5事業年度において、FC契約に関する訴訟の件数営業時間・営業日及び休業日本部事業者が加盟者の店舗の周辺の地域に同一又は類似の店舗を営業又は他人に営業させる旨の規定の有無及びその内容契約終了後、他のFC事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業禁止又は制限される規定の有無及びその内容契約期間中・契約終了後、当該FC業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合はその時期及び方法加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付の斡旋を行う場合は、それに係る利率又は算定方法及びその他の条件加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利率を附する場合は、利息に係る利率又は算定方法その他条件加盟者に対する特別義務契約に違反した場合に生じる金銭の支払いその他義務の内容加盟に際し徴収する金銭に関する事項加盟者に対する商品の販売条件に関する事項経営指導に関する事項使用される商標、商号その他の表示契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項 開示書面のチェックポイント ○ 加盟店のサポートや援助に関する項目 フランチャイズ契約では、加盟店は本部から継続的なサポートが受けられることが通常です。 内容としては本部社員(スーパーバイザー)が1カ月にどれくらいの頻度で巡回にくるのか、また具体的にどういったサポート、指導、運営のアドバイスなどを本部から受けることが出来るのかなどを把握しておくのがポイントとなります。 ○ 競業避止義務に関する項目 競業避止義務は契約期間中と、契約終了後の一定期間適用されるものがあります。この義務が定められる目的は、本部の持つノウハウの保護と、フランチャイズの商圏の維持の2つが主です。 しかしながら、加盟者の営業の自由を脅かすような内容であってはならないため、合理的な内容となっているかを確認しましょう。 ○ ロイヤルティに関する項目 フランチャイズ本部のノウハウや商標を使用することに対する対価で、基本的には毎月加盟者が本部へ支払うのが一般的です。 ロイヤルティの形式は大きく分けて2つあり、毎月の売り上げに対する割合で算出する方法と、固定額を毎月支払う方法と、フランチャイズ本部により様々あるので確認しておきましょう。 売上に対する割合で支払う場合、対象となるのは売上総利益なのか営業利益なのかはフランチャイズ本部により異なるので確認しておきましょう。 ○ フランチャイズ本部の財務状況の項目 一般的に企業の財務状況を判断するには成長率、収益性、生産性、安全性の4つのポイントから総合的に判断します。事業経過年数により、それぞれのポイントの判断基準は異なるため、下記に記載するフランチャイズの成長段階表を参考にしながら総合的に判断するようにしましょう。 フランチャイザーの成長段階のステージ別区分 成長段階のステージフランチャイジー数シードステージ期5店以下アーリーステージ期20店以下ミドルステージ期80店以下レイターステージ前期80~300店レイターステージ中期300~500店レイターステージ後期500店以上 ○ 成長率 売上高や店舗出店数が毎年プラスとなっている状態が望ましく、シードステージに近いフランチャイズ本部ほど、急成長してこの部分が良好になる傾向にあります。 ○ 収益性 売上に対する営業利益率や売上総利益率、総資本に対する経常利益率が該当します。特に総資本に対する経常利益率は、そのフランチャイズ本部の経営成績が一番把握しやすい数値となります。 ○ 生産性 売上高を坪や従業員単位で算出します。シードステージからアーリーステージではこの値が良好になる傾向にあります。理由としては従業員数が少なく、優良店舗が多い傾向にある為です。 ○ 安全性 フランチャイズ本部の資金運用状況を判断する上で、主に以下の点を確認します。 自己資本率流動比率固定長期適合率 固定長期適合率とは、固定資産、自己資本、固定負債の合計からそれぞれの割合を示す数値です。固定資産が安定して運用されているか、財務状況が正常であるかの判断をするうえで最も重要な指標となります。 ○ 直近5年間のフランチャイズ契約に関する訴訟数 フランチャイザーとフランチャイジーの関係性を判断することができます。訴訟があるからと良くない本部とはらないので、どういった内容の訴訟なのか、きちんと説明受けるようにしましょう。 ○ テリトリー権について テリトリー権とは、既に出店している加盟店の商圏内に後発の加盟店が出店することができないという契約です。もしこの権利が認められている場合には、自分の出店予定エリアに既に出店している加盟店、または今後出店予定の加盟店があるかを確認する必要があります。
-

7.物件についての検討方法(「面・線・点」で考える)
フランチャイズで起業する場合、店舗を構えた起業をする方が多いと思います。 店舗の立地はビジネスを成功させる上でとても重要です。また、いくらフランチャイズ本部の恩恵を受けることができても、本部の努力で変えることはとても難しいのがこの店舗の立地です。 これから紹介するポイントを押さえておけば、立地で大きく失敗する可能性が低くなるので是非ご参考ください。 立地条件の把握 まずは、加盟したいと考えているフランチャイズ業態の「立地基準」をきちんと理解しましょう。いくら条件の良い立地を見つけても、この「立地基準」をクリアしていなければフランチャイズの看板で開業することが出来ません。 ビジネスや経営思考で「点、線、面」というワードがよく使われ、「点」から始まることが多いですが、ここで紹介する「点、線、面」は「面」からのスタートし、「点(立地)」を検討する考え方です。 立地は空間を相対的に評価し、その中の一番よい「点」を選ぶことです。よく「点」だけを見てしまったり、点から面を後付けで考えてしまったりする人がいますが、それでは良い立地条件を見つけることが難しいですし、結果フランチャイズとして起業しても成功できる確率は低くなってしまいます。 ここで紹介する立地は、面、線、点の順番で検討していき、全てが基準以上に該当する「点」を立地ポイントとします。 「面について」 「面」=商圏を指します。商圏から物件を検討することが重要です。対象とするユーザーが多くいるエリアを把握しましょう。 実際のデータは商工会議所や役所で手に入れることができるでしょう。そのデータをもとにいくつか商圏の候補地を挙げておき、今度は実際にその商圏を訪れてみてください。 これから展開しようとしている事業がこのエリアとマッチしているのか、見込める客層は潤沢にいるかなど、時間帯を変えたりして何度か訪れてみることをお勧めします。データだけでなく現地を自分の目で確かめることは重要です。 以下にチェック項目を掲載しておきますのでご参考ください。 チェック項目収集方法1.商圏人口・世帯数・伸び率住民基本台帳・国勢調査2.年齢別人口比率(ターゲット比率)住民基本台帳・国勢調査3.昼間人口国勢調査4.居住形態(賃貸、持ち家比率など)国勢調査5.所得水準地域経済総覧(東洋経済新報社)6.家計支出水準家計調査年報7.貯蓄水準地域経済総覧(東洋経済新報社)8.地元購買率消費購買行動調査(県、市町村)9.通勤通学先国勢調査10.自家用車保有率地域経済総覧(東洋経済新報社) 「線について」 線=動線、導線です。検討候補の物件には対象となるターゲットとなるユーザーが実際に多く往来するかどうか、また、その通行する道路から自店舗を見つけやすいかなどの導線を検討します。 奥まった立地であるとか、反対側の歩道からは遮蔽物によって見つけにくい物件はなるべく避けるようにしましょう。また、競合店舗などの立地も把握しておく必要があります。例えば自店舗よりも駅に近い競合がある場合、そちらにターゲットが流れてしまう恐れが十分にあります。 周辺環境のメリット、デメリットをしっかりと把握したうえで複数候補地を挙げておき、現地を確認していきましょう。 チェック項目収集方法1.候補地の分かりやすさ実地調査・現地ヒアリング2.商圏内の消費者動線の方向地図読み取り・実地調査3.商店街(マグネット)など中心地からの店舗位置地図読み取り・実地調査4.車線の面する方向(上り側、下り側)地図読み取り・実地調査5.商圏分断要因(バリア)の存在地図読み取り・実地調査6.候補地前通行量(歩行者・)実地調査・道路交通センサス7.候補地前通行料(車両)実地調査・道路交通センサス8.競合店舗数電話帳・業界リスト・実地調査9.立地の優位性(対競合店)実地調査10.今後の競合店の出店予定実地調査 「点について」 点=立地場所です。いくら「面」「線」の条件を満たしていても、フランチャイズチェーンの標準店舗面積よりも小さい物件では加盟することができない場合もあります。事前に立地基準を把握したうえで調査をしましょう。加盟する前に物件を決めてしまいたい気持ちもわかりますが、できればしっかりと立地基準を確認してから決定するようにしましょう。 見つけやすい立地かどうか、道路に面していて車などの出入りがしやすいか、道路を挟んだ反対側からでも見つけやすい立地か、周辺環境はどうかなど検討してみてください。 特に見つけやすさに関しては、自分の店舗が見つけやすい立地にあるだけで宣伝としての効果が大きいです。障害物や大通りから見て大きな建物の陰になってしまっていると、これは大きなデメリットだと考えてください。 チェック項目収集方法1.候補地前障害物や遮蔽物の有無実地調査2.候補地の視認性実地調査3.候補地の立地条件(角地、一面)実地調査4.道路との設置幅(間口)公図・実地調査5.地形(土地の形など)公図・実地調査6.車両の入出庫のしやすさ実地調査7.道路との段差実地調査8.駐車場の確保の有無(同一敷地内か)実地調査 「基準点」以上が立地の条件 物件選びのポイントは「ターゲットとなるお客さんが沢山いるエリア」で「お店に足を運びやすい場所」で「見つけやすい」の3つが条件になります。 どれか一つでも欠けていると条件に満たないので、そこに店舗を構えることはお勧めできません。 また、ここでのデメリットは他でカバーすることが非常に難しくなります。「ちょっと見つけにくいけど、ターゲットとなるお客さんは沢山いるエリアだ」という考え方はNGです。 しっかりと時間をかけて自分の目で現場を確認し、基準点以上の立地を見つけましょう。
-

8.事業計画書を作るためのポイント
事業計画書はフランチャイズで起業した後、将来のロードマップのようなものです。 どう言った形で自分のビジネスを進めていくか、どんなアイディアがあるかなど、まずは色々と書き出していくことが大切です。思いついたときに、形式問わず、アイディアをどんどん書き出してみましょう。 そして、一通りの案を出すことができたら、出てきた案を見直してみましょう。以前書いた案をもう一度振り返ることで、より良いアイディアが生まれるかもしれません。 このように「書き出す」→「振り返る」→「考える」を繰り返すことでよりよい事業アイディアとなり、ビジネスを成功に導いてくれる事業計画となります。 以前の記事の「2.なぜFC起業するのか6W2H(FCを開業するための頭の整理)」などをベースに書き出してみるとアイディアを出しやすいかもしれません。 事業計画書は開業後のロードマップ 完成した事業計画書は、事業を進めていく上で迷ったり、不安になったりしたときに道を示してくれるものになります。もしも、これを作らずに事業をスタートしてしまうと、一体どっちに進めばいいかわらず、間違った方向に進んでしまったり、その場に立ち止まったりしてしまいます。 フランチャイズ起業を決めた時の想いを、事業計画書を読み返して思い出し、ビジネスを成功させるために、しっかりと成功に向かって事業を進めていきましょう。 また、事業計画書は銀行の融資を受ける際にも必要となってくる書類です。ここでは事業計画書の抑えておくべきポイントを紹介します。 事業計画書のフォーマットは? 事業計画書は特に決まったフォーマットはありません。したがって自由に作成することが出来ますが、内容としては以下の点を抑えておきましょう。 事業の目的事業内容マーケティングの手法売上目標、利益予測資金繰り方法(開業資金計画・収支計画)創業者、創業メンバーのプロフィール 上記以外には学歴や職務経歴を記載します。取得資格など「この人だからこのビジネスを行うことで成功できる」ということが分かるプロフィールにしましょう。事業と関係のない経歴は不要です。 事業の目的と将来のビジョン 「このビジネスを通して世の中の暮らしを豊かにしたい」、「こんな会社にしたい」など、目標やビジネスをスタートするきっかけとなった熱い想いを伝えましょう。 事業内容 どのマーケットで、どんなユーザーをターゲットに何を売るのか、どんなサービスを提供するのか、それらがどういった魅力があってターゲットが買いたいと思うのかなどをまとめましょう。 なるべく簡潔に誰にでも分かるように書くことがポイントです。 強みと特徴 競合のサービスとどう違うのか、何が他のサービスよりも優れているのか、サービスのポイントは何かを明確にしましょう。他と同じようなものでは、先にスタートしている方が有利なので選択する候補に上がりづらくなってしまいます。競合分析をしっかりと行って、自分たちにしかできない方法を検討し、記載しましょう。 市場環境と競合について 事業を取り巻く市場環境と、脅威となりうる競合などについて検討しましょう。強みと特徴の部分に類似しますが、競合他社との差別化ができていること、独自のアイディアで付加価値を高める点をまとめます。 販売戦略(マーケティング) 自分の商品をどのような形で利用してもらうか、アピールしていくかを検討します。 人員、販促費など具体的に人数や金額などを設定しても良いかもしれません。 仕入れと売上計画 売上プランを立てる際は商品別、サービス別など、細かい項目ごとに出しましょう。また、その裏付けとして見込み顧客やFCの経営指標などを参考にし、リアルな目標設定をしてください。 原価売上計画を立てるときも同様に細かい項目に分けておくようにします。こうすることで振り返りの際にどの部分がストロングポイントなのかを見つけやすくなり、その部分を伸ばしていくことで効率的に事業を成長させることができます。 利益計画 利益計画は融資などを受ける際に最も重要視されるポイントです。利益を予測する際にまずは以下の内容を順番に予測しましょう。 売上→売上原価→人件費→減価償却費→販売費→管理費→借入利息→法人税等 これらを予測することで以下の利益を予測することができます。 売上総利益→営業利益→経常利益→税引後利益 利益を出すフランチャイジーになるためには、どこで売上げ、どこの費用を下げる必要があるのかが見えてきます。 資金調達計画 利益計画同様に重要なポイントです。 利益が出ていてもそれはイコール「資金がある」ということにはなりません。融資を受ける際には、返済可能な資金があるかどうかが融資を受けられるポイントとなってくるので、自己資金がどれだけあるかを明確にしておきましょう。
-

9.フランチャイズ加盟契約のフロー
基本的なフランチャイズ加盟契約までのフローは下記です。 (1)本部開催の説明会参加(2)個別説明会に参加(店舗視察、費用関連の説明)(3)立地調査(4)フランチャイズ契約、法定開示書面の交付(5)契約書の取り交わし(6)加盟 契約書は受け取って、その場で署名、捺印するのではなく、一度持ち帰って内容をしっかりと納得、理解した上で契約を結ぶようにしましょう。 契約書を確認する上でのポイントを紹介します。 フランチャイズの商標 本部が特許庁へ商標登録を終えているか確認しましょう。 加盟金、ロイヤルティなどの費用 本部へ対しての支払い義務のある費用を確認しましょう。また、それらは何の対価ための費用なのか、返金の有無など、すべての費用において明確にしましょう。 テリトリー権 テリトリー権とはフランチャイジーに対して一定の地域で独占的に営業を保証するものです。この権利が保証されていない場合には、同業者の出店予定がないか事前に本部に確認しておきましょう。 研修 フランチャイズで開業する場合、数週間〜数ヶ月の研修を受けることがあります。研修スケジュール、費用など確認しましょう。 店舗運営と経営指導 フランチャイズでの仕入れは本部の指定業者からが多いです。また、経営指導に関してはスーパーバイザーにより行われることが多いです。担当のスーパーバイザーはどう言った人か、派遣頻度やその費用など店舗運営に大きく影響する部分でもあるので確認しておきましょう。 契約終了について フランチャイズ契約には契約期間が定められています。加盟者はその期間内に初期投資を回収できるかどうかを確認しておきましょう。 また、契約更新は自動更新か、更新の手数料の有無、途中解約の違約金などが発生するかなども確認しておきましょう。 フランチャイズ契約は軽微な義務違反程度では解除されません。また、途中で解約する際はそれなりの理由がないと、信頼関係を失う事にもなりかねないので注意しましょう。 守秘義務 本部の営業のノウハウや営業秘密を第三者に開示した場合、損害賠償や高額な違約金を請求される可能性があります。守秘義務は契約解消後も一定期間継続します。 競合の禁止 加盟者が契約期間中、または契約終了の数年間に類似事業を行うこと禁止します。これも上記同様違反すると高額な違約金を請求されることがあります。 その他の契約について 加盟者が店舗準備をする際には、物件が決まってから、内装や設備の準備をしなくてはいけません。普通はフランチャイズ契約とは別に賃貸借契約やリース契約を締結します。その際の書面に「フランチャイズ契約が解消された際に本契約も終了する」という記載されていることがあります。 このような制約の場合、加盟者がフランチャイズ契約を解約したくても、リース残額や物件の途中解約違約金など高額な支払い義務が発生するため、実際に解約できなくなってしまう場合があるので注意しましょう。
-

10.事業開始準備
会社員から個人事業主になる際にやるべきこと 会社を退職して個人事業主でフランチャイズ起業をする場合、主な手続きとしては「国民健康保険」と「国民年金」への切り替え手続きをする必要があります。 国民健康保険へ加入 個人事業主になる場合、「国民健康保険」へ加入することが義務となっています。国民健康保険に加入するには、会社を退職したことの証明ができる下記のいずれかの書類が必要です。 健康保険資格喪失証明書退職証明書離職証その他退職したことがわかる書類 また、注意しないといけないのは、この手続きの期間は退職してから「2週間以内」に手続きをしないといけません。居住している地域の国民健康保険の担当窓口で手続きをしましょう。 手続き可能期間が短いため、会社には在籍中に依頼しておきましょう。実際に資格を喪失するのは退社日の翌日のため、通常は在籍していた会社から退社日以降でないと発行してもらえませんが、会社が発行する証明書なので、退社日よりも前に準備してくれる事もあるようなので確認してみてください。 国民年金へ加入 国民年金の手続きは国民健康保険に比べて必要書類の事前準備もなく簡単に申請することができます。 国民健康保険同様、退社日から2週間以内に居住地域の国民年金担当窓口にて、手続きできます。手続きをする際には年金手帳が必要になります。 所得税や住民税の申告において、国民年金保険料は全額が社会保険料控除対象となります。個人事業として起業する際の節税対策にもなるので必ず申請するようにしましょう。 個人事業としてスタートを切る まずはしっかりと実績を積み、事業を安定させるために個人事業主からスタートしましょう。法人は定款という、会社のルール的なものがあり、法人化してしまうと名前や事業内容を変更することが容易にはできなくなります。 色々と模索しながらビジネスを成功へ導くためには多少の事業内容の変更も可能性としてはあるので個人事業主としてまず始めて見てください。 個人事業主でも屋号を付けて活動可能で、変更も容易にすることが出来ます。ただし、XX会社、○○法人などを入れることは禁止されています。共同経営者や従業員も雇うことが出来ます。 ただし、デメリットもあります。 公共事業などは発注要件を法人に限定しているところが多いこともあります。法人を対象とした補助金制度などは個人事業主が受けることが出来ませんので注意しましょう。 個人事業主になる為に必要な手続き 税務署に「開業届」を提出するだけで個人事業主になることができます。以下の国税庁のURLから書類をダウンロードすることが出来ます。[個人事業の開業届出・廃業届出等手続] (国税庁) 税務署にも同一の書類がありますので、必要事項をその場で記入し提出することも可能です。記載する情報は個人情報と事業に関する「事業内容」「屋号」です。屋号は特にない場合は空欄での提出でも問題ありません。 所得税の青色申告承認申請書の提出 確定申告には大きく分けて「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は申告方法が簡単ではありますが、節税メリットがあまりありません。 青色申告は、複式簿記や簡易簿記等の正式な簿記記帳によって申請する必要がありますが、所得控除などの優遇措置を受けることができ、節税効果が高くなります。[所得税の青色申告承認申請手続](国税庁) 小規模起業共済 万が一、自分のビジネスが上手くいかず、お店を畳むことになった際の生活資金を積み立てておく事業主向けの「退職金制度」の一種です。 こちらも掛金は全額所得控除となる為、節税対策になることと、事業資金の借入制度もある為おすすめです。 中小機構「小規模企業共済」
-

11.独立資金の調達
資金準備 開業において重要なのはお金です。ある程度余裕を持った資金調達をしないと事業スタート後の資金繰りに影響してしまうことともあるので気を付けましょう。 一部借入をする事になる場合があります。少なくとも必要資金の50%以上は自己資金で賄えるようにし、余裕を持った返済ができるようにしましょう。 資金プランの見直し 一度必要資金を洗い出したら、後日その資金プランを振り返ってみましょう。別の考え方をすれば資金を抑えることができるかもしれません。無理な資金調整はビジネスを遂行する上で逆効果になってしまう可能性がありますが、資金プランの見直しは重要なポイントでもあるので何度か見直し最適化しましょう。 また、客観的に確認してもらうことも重要です。先入観で減らせる部分を見落としていたりする部分に気づくことができます。 資金調達に関しては大まかに以下の分類に分けることができます。 自己資金 預貯金、退職金、有価証券など 親族や友人、社員などからの出資、借入 返済条件に融通が効きやすい特徴があります。場合によっては自己資金の部類に入ることもあります。 外部からの出資 ベンチャーキャピタルから出資を受けることができる場合があります。条件としては将来的に上場の見込みがある場合です。 外部機関からの借入 銀行や協会から借入をすることができます。 公的金融機関:日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、市町村の融資斡旋制度など 民間金融機関:都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など その他 車両や什器などをリースで借り受けることができます。購入するとその分の資金が必要になるので、この場合資金調達として考えることもできます。 自己資金の増額 自分の身の回りの資産などを見直してみましょう。自動車などはリースをすることが可能です。自分の愛車を手放し現金化することができます。また、保険の見直しも1つの手です。不要な出費を抑えることは資金調達の第一歩です。もし今はまだ会社員であれば、今のうちから計画的に貯金をして将来の開業資金を増やしておきましょう。 融資してもらう 融資で借入できるのは無担保で3000万円が限度です。それ以上を借り入れたい場合はそれに見合った担保を提供する必要があります。融資のメリットは金銭貸借上の関係なので経営に関してはそこまで踏み込まれない点です。 また、こちらは「借入」なので一定期間に返済する必要があります。 出資してもらう 出資は会社や法人の一部、または全部の所有者になってもらうことです。出資なので返済の必要はありませんが、代わりに経営に関して出資者が議決権を持ちます。経営に関して色々とアドバイスを貰えますが、場合によってはそれがデメリットでもあります。しかし、予め議決権の範囲を制限することもできます。 融資の種類 融資といっても金融機関や自治体など様々です。公的資金からの借入をする方が融資の条件や返済期間など、新規事業者に対しての負担軽減をしてくれるところが多いためおすすめです。 日本政策金融公庫 日本制作金融公庫の国民生活事業は、新規開拓業者に対しての融資を得意としています。 全国に窓口があり、対応業種も幅広く、融資実績は創業前、創業1年未満の起業へ10年間で20万社以上になります。 上限3000万円の範囲で無担保・保証人不要で新規事業者向けの融資制度もあります。(運転資金として1500万円) 開業時の返済負担軽減のための元金措置期間も設定可能で、初期の月々の返済額を抑えることもできます。 沖縄県は沖縄振興開発金融公庫が同様の融資を行っている。 地方自治体 その地域に住む人や事業所を構える人を対象に融資制度を設けています。市区町村の自治体の場合、利子補給制度を使った金利の一部を負担してくれる制度を用意しているところも多くあります。 また、起業をする業界での経験が少ない事業者を対象とした自治体主催セミナーに参加することを条件に融資を行う地域もあります。 国が認めた市町村の特別事業支援事業を利用した事業者(市町村の実施するセミナーを受講)は市町村が発行した証明書を持って株式会社を設立する場合、登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などを特例で受けることができます。各自治体により様々なので詳細は問い合わせてみてください。 民間金融機関 地方銀行や信用金庫、信用組合など、地域密着型の機関を中心に、独自に資金融資制度を行なっている民間金融機関も多くあります。 特徴としては店舗型のビジネスを中心とした開業資金の融資が多く、それとは別に信販会社やリース会社もある。
-

12.開業後のポイント
フランチャイズで起業することがゴールではありません。開店の数週間前などはオープン準備で寝る間も惜しんで徹夜で準備をされるオーナーさんもいます。 まずは、ビジネスを軌道に乗せるまでを目標に責任者としての責務を果たしましょう。 フランチャイジーの役割と責任 フランチャイズで起業をしても、あなたは独立している会社のオーナーであり、経営者として経営責任があります。下記に挙げるポイントを押さえておきましょう。 経営管理 予算、目標、売上高、経費、利益実績、などの分析、方策を行い実行していきます。本部から過去の実績や分析データなどを参考に計画的に管理しましょう。 店舗運営 フランチャイズとしてブランドイメージに合った営業方法やサービスの提供に努めましょう。また、本部からは適正な人員配置と業務効率を求められますので、効率的な無駄のない運営を検討していきましょう。 販促活動 本部と相談しながら自店舗にあった販促手法を検討しましょう。本部提供の商品、サービス、広告はフランチャイズならではの特権であるので、最大限に活用し集客していくようにしましょう。 投資について ビジネスを成功させる上では、ある程度のリスクを負うシーンは出てきます。そのリスクは先行投資であるという意識を持ち取り組んでいくことが大切です。 人材の教育 一度に多くの人を採用すると、一度に新人教育を行う必要があるので大変です。まずは数人を採用し、彼らをしっかりと育成して、ゆくゆくはマネージメント的なポジションを任せることのできる人材となることが理想的です。 本部との連動とコミュニケーション 自身のビジネスを成功させるためには、本部との連携も重要です。フランチャイジーの事業成功、安定化のために本部は日々努めています。加盟店は業績を上げることによって本部へ貢献することが出来ます。このwinwinな関係をお互いに持つことがお互いのビジネス成功のカギとなります。 スーパーバイザーについて 加盟店に経営のアドバイスをしてくれる人のことです。また、現場が日々感じているお客様の動向や、商品、サービスの売れ行き、不満、要望などをヒアリングし、本部に持ち帰り、キャンペーンの検討や改善策を図るなど、本部との橋渡しの役目を担っています。 加盟店はスーパーバイザーとの関係性を大切にし、有益な情報を共有してもらいましょう。フランチャイズ本部毎にスーパーバイザーの訪問頻度は異なりますが、あまりにも訪問回数が少ないと良い関係性の構築は難しく疎遠になってしまうので気を付けてください。 フランチャイズ本部とのコミュニケーション 加盟店オーナーを対象とした情報交換の場として、オーナー会や交流会を定期的に行っているフランチャイズ本部もあります。こういった機会は本部からの意見とはまた違った視点からの話を聞くことが出来ます。積極的に参加し、本部の経営方針や経営戦略に関しても理解も深め、事業の向上へ反映させましょう。 FCのノウハウを活用する データの活用 本部には全国のフランチャイズ店の様々な情報が集まっています。そのデータを共有してもらい、自店と比較しながら経営戦略に活用しましょう。 特に売り上げや利益の推移に関しては自店の状況把握のツールにもなります。 本部マニュアル フランチャイズ事業を標準化するために必須な教育ツールです。今までのフランチャイズとしてノウハウが十分に詰まった資料となるので、開業後、問題点や困難に直面した際には、改めて読み返してみましょう。 内容に関して、実際に店舗を運用してみて、疑問点や改善点などが出てくるかもしれません。そういった場合にはスーパーバイザーに相談してみたり、オーナー会で他店舗の店長たちと意見交換することで、新たな運用方法を思いつくかもしれません。 契約の継続と終了 契約が終了するタイミングとしては契約期間の満了、いずれかの責務不履行による解除、フランチャイズ契約の中で定められた解除事由による解除(約定解除)、両当事者による合意による契約の終了などがあります。 契約期間の満了 3年契約、5年契約、長いものでは10年契約などがあり、標準的な期限は特にありません。 フランチャイズ本部が契約期間を設定する場合、加盟店が初期投資額を十分に回収できるだけの期間を設定するのが通常です。 現在の国内でのフランチャイズ契約では5年契約が一番多い様です。 法定解除、約定解除 本部または加盟店のいずれかに責務不履行があった場合、もう一方は民法に基づき契約を解除することができます。 責務不履行の事由に関しては、フランチャイズ契約をする際の契約書に通常全て記載されているので、本部は加盟店の責務不履行についてはその契約書に戻付き契約を解除することが出来ます。 また、場合によっては契約期間中でも申請によって解除できる場合もありますが、途中解約には高い違約金を支払う必要があったり、リース設備の残金支払いがあったり、物件の途中解約によるペナルティーなども発生し、多くの資金が必要になるため注意しましょう。 合意解約 本部、加盟店双方が合意する場合、契約を解除することが出来ます。その場合は、契約解除における合意書を作成することをオススメします。 トラブルの現状と回避のための基礎知識 契約締結時のトラブル フランチャイズ契約をするにおいて、本部が売り上げ予測を立てて、加盟者に提示することがあります。あくまで予測なので、そのまま鵜呑みにする必要はありません。また、加盟者は独立した事業者でもあるので、それが達成ノルマでもありませんので安心してください。 しかし、明らかに合理性のない予測を加盟者に提示し、契約締結の判断を極端に誤らせる情報として提供したと判断された場合は、本部は情報提供義務違反となります。 加盟金変換に関するトラブル 多くのフランチャイズ契約では「一度支払われた加盟金はいかなる理由があっても加盟店に返還されない」という決まりになっています。(加盟金不返還特約)。一度契約を締結すれば、本部は加盟店に対して、商標の使用許可、研修、ノウハウの提供などを行うため、加盟金の対価性は満たされるため、上記の特約は妥当とも言えます。 近年、特定のエリアエントリー契約という、「特定のエリアで出店するための営業権」を付与するフランチャイズ本部が出てきています。 店舗物件が確定する前に締結できる契約のため、結果的にそのエリアに出店できなかったというトラブルが発生しています。 エリアエントリー契約の場合は、きちんと出店できる物件の目星をつけておきつつ、出店できないリスクも考慮したうえで契約を結ぶようにしましょう。
-

はじめてのフランチャイズ起業|成功確度を高める準備とリスク管理
フランチャイズ起業は「数字」「契約」「現場」をそろえると、グッと安心して進めます。勢いだけに頼らず、落ち着いて準備していきましょう。数字で判断して、契約で守って、現場で確かめる――この順番を意識するだけで迷いが減ります。 まず押さえる前提:「フランチャイズは準備9割」です 不安、ありますよね。大丈夫です。順番を決めて、一つずつやっていきましょう。あらかじめ「ここまで整わなければ今回は見送る」という自分ルールを作っておくと、決断がラクになります。 動機は立派じゃなくてOKです。「家族の時間を守りたい」「働き方を変えたい」「自分のお店を持ってみたい」。自分の言葉で説明できれば十分な出発点です。家族との話し合い、現職との向き合い、資金のあたりを同時に少しずつ。あと戻りのコストを小さくして進みましょう。 自己診断:ライフプラン×起業動機×リスク許容度 ここは背伸びせず、等身大でいきます。見るのは「お金」「時間」「性格」の3つだけ。シンプルにいきましょう。 お金は、家計の実際の支出と貯蓄、ローンの有無を書き出します。できれば生活費の半年分を“別腹”で確保。心の余裕がぜんぜん違います。 時間は、開業直後に自分が現場へどのくらい入れるかをイメージします。最初は思った以上に現場に入ります。体力と家族の理解、ここが支えです。 性格は、採用や育成が好きか、数字を見るのが苦じゃないか、クレーム対応はどうか。苦手があっても大丈夫。本部の支援や外部の力で補えるなら選択肢になります。どうしても補えない“致命的な苦手”だけを、やめる基準にしておきましょう。 事業選定の軸づくり 資料をたくさん集める前に、“選ぶ軸”をサクッと決めておきましょう。軸があると、うまい話に流されにくくなります。 収益モデルは安定しているか。季節や天気の影響は強いか。価格を動かしやすいか。ここを見ておくと、手元に残るお金のイメージが持てます。ロイヤリティ(本部へ払う対価)の方式も大切です。売上に連動か、毎月定額か、粗利に連動か。方式の違いで、同じ売上でも利益が変わります。 再現性は、誰がやっても似た結果になりやすい仕組みがあるかどうか。マニュアル、研修、発注・在庫の流れ、仕入れの一本化。ここが整っていると、初めてでも安心です。 人材への依存度はどうでしょう。採用が難しい職種か、教育にどれくらい時間がかかるか。人件費の比率が高い業態ほど、人の定着が利益に直結します。本部の採用支援や教育カリキュラム、遠慮なく聞いて確かめましょう。 立地への依存度も見ておきます。駅前一等地でないとダメなのか、住宅地や郊外でも回るのか。宅配やサブスクが使えるなら、立地の幅が広がって安心感が増します。 許認可は地域で差が出ます。保健所や消防の手続き、必要な資格者の配置など。わからないことは「わからない」でOK。素直に本部や自治体に確認していきましょう。 資金計画の基礎:初期投資と運転資金 お金の話、ここで一度整理しましょう。ポイントは「一度きりの費用」と「毎月の運営を支えるお金」に分けることです。 一度きりの費用(初期投資)は、加盟金や保証金、内装・設備、看板、システム、開店前の人件費、研修費、細かな備品など。名称は本部ごとに違うので、内訳と税込・税抜を必ず確認しましょう。 毎月の運営を支えるお金(運転資金)は、黒字化までの赤字や入金のタイムラグを埋めます。目安は、家賃や基本給など“売上ゼロでも出ていく費用(固定費)”の3〜6か月分。ここに余裕があると、判断が落ち着きます。 自己資金の割合に“正解”はありません。業態、地域によって変わります。特定の数字に縛られず、複数の金融機関で率直にヒアリングしてみましょう。金利や期間も同じです。断定はせず、その時の最適解を取りに行きましょう。 返済計画は、「事業が生むお金で無理なく返せるか」を示せばOK。そこで役立つのがDSCR(返済余裕倍率)です。意味は「返済に回せるお金 ÷ 毎月の返済額」。1を超えたら返済可能、1.5以上だと安心、くらいの感覚で十分です(厳密な式は金融機関で少し変わります)。 月次シミュレーション:損益分岐点と返済可能性 難しいソフトは不要です。A4一枚の“月次PL(損益表)”を作ってみましょう。売上→原価→人件費→家賃→水道光熱→ロイヤリティ→広告分担金→その他経費。順に並べるだけで、数字の会話が驚くほど進みます。 ここで2つだけ用語をご説明します。損益分岐点売上=赤字と黒字の境目の売上。考え方は「固定費を、売上から残る利益(限界利益)でまかなえるライン」。感度分析=売上や費用が少し動いたとき、利益がどれだけ動くかの“予行演習”。 流れをつかむため、仮の数字でイメージしましょう。月の売上300万円、原価30%、人件費25%、家賃30万円、水道光熱15万円、ロイヤリティ5%、広告分担金2%、その他15万円。営業利益は54万円。返済20万円なら、ゆとりがあります。では売上が10%下がったら? 270万円だと営業利益は約35万円。まだ返せますが、余裕は薄くなります。こうして“揺れ幅”を事前に見ておくと、開業後に慌てません。 損益分岐点も出しておきましょう。固定費が150万円、変動費率(原価+売上連動の費用)が37%なら、限界利益率は63%。150万円 ÷ 0.63 ≒ 約238万円。月30日なら1日あたり約7.9万円。毎日の目標がパッと見えるようになります。 本部の見極め方:情報開示書面とFC契約書の必須チェック ここは“自分を守るステップ”です。情報開示書面が薄い、本部の説明が曖昧――そんなときは黄色信号。遠慮なく質問していきましょう。 契約書は長くて大変。ですが、見るコツを押さえれば怖くありません。ロイヤリティの算定方法(売上連動・定額・粗利連動)で負担が変わります。売上の定義にクーポンや宅配手数料は含むのか、ここは早めに確認。広告分担金は、本部の全国広告と各店の販促の“境界線”をはっきりさせましょう。見直しルールも一緒に。テリトリー(出店範囲)は、自店のすぐそばに同ブランドが来ないかを決める大事な項目です。オンラインや宅配の扱いもセットで確認。契約期間と更新、途中でやめる場合の取り決めも要チェック。更新料、解約の条件、違約金、退去時の原状回復の範囲、看板や機器の撤去費の負担先まで、スッキリさせましょう。仕入れ先の指定があるなら、価格の妥当性や代替不可の品目、物流トラブル時の対応も聞いておくと安心です。教育・サポートは、研修の時間、オープン支援、定期フォロー、売上不振時の“実際のテコ入れ事例”まで見せてもらいましょう。 口頭の約束は期待しすぎず、必ず文書に。メールで履歴を残しておく。これだけで、後のモヤモヤがかなり減ります。 現場での“再現性”検証 各種資料も大事。でも、やっぱり現場が一番の教科書です。黒字店だけでなく、伸び悩み店にもお願いして見学やヒアリングをさせてもらいましょう。 聞きたいのは「事実」と「数字」。開業からの売上の流れ、平均客単価、ピーク時間、採用人数と離職の理由、追加投資、原価の上がり下がり、値上げのしやすさ。本部サポートの実感も“温度感”で聞くとリアルです。数字がもらえないときは、そのこと自体を情報として受け止めればOKです。 体験入店ができるならベスト。未経験でもマニュアルどおりに回せるか。レジや端末、在庫・発注、清掃までが一つの流れでつながっているか。店長不在の時間帯でも無理なく運営できるか。ここに“再現性の核”があります。 物件と商圏:数字で選ぶ 良い本部でも、立地が合わなければ苦戦します。だから、ここは“数字で落ち着いて”。一次商圏(徒歩など近距離)と二次商圏(車・自転車など広め)のイメージを持って、平日と休日、昼と夜、晴れと雨で街の顔を見に行きましょう。 視認性、導線、駐車のしやすさ、競合の距離感。地図で仮説、現地で確認。これがコツです。家賃は売上とのバランスで判断します。業態によって良い比率は変わるので、本部が持つ“目安の根拠”を聞かせてもらいましょう。共益費、看板使用料、保証会社の費用、更新時の賃料見直しなど、付随費用も忘れずに合算です。 物件を比べるときは、同じものさしで。間口、天井高、柱の位置、バックヤード、排水・電気容量、ダクト可否。居抜きは工期・コストで助かりますが、レイアウトの自由度が下がることも。退去時の原状回復条件は最初に確認して、将来の“びっくり出費”を避けましょう。 開業90日ロードマップ 開業準備は「お金・人・場所」の三本柱を同時に少しずつ進めると、スムーズに進められます。ここでは“今日から90日”をイメージしながら、週ごとの動きを描いていきます。完璧でなくて大丈夫。目安として使ってください。 Day 1〜14:設計図をつくる時期です。 本部とのヒアリングを深め、情報開示書面と契約書のポイントをもう一度チェックします。資金は金融機関へ早めに事前相談。ここで「自己資金はどのくらい用意すると良いか」「どんな資料が必要か」を聞いておくと、後がスムーズです。並行して、商圏の一次調査と物件の仮押さえ候補をいくつか作っておきます。 Day 15〜30:意思決定のコアを固めます。 候補物件を絞り、現地チェックを昼・夜・休日で繰り返します。既存オーナーへのヒアリングはこの時期がベスト。採用計画のたたき台(何名・どの役割・いつから必要か)を作り、求人媒体や紹介会社に事前相談します。融資は必要書類の収集を開始。粗い月次PLとキャッシュフローの見取り図を作り、本部にも共有して“数字の温度感”を合わせておきます。 Day 31〜45:契約と資金の山場です。 物件の基本条件がまとまったら、本部とのFC契約を進めます。契約前に気になる条項があれば、ここで解消してから署名へ。融資は本申込に入り、資金の着金タイミングを逆算して工事や仕入れのスケジュールを組みます。店舗のレイアウト設計と見積のすり合わせもこの時期。POSや決済端末、通信回線など“後回しにすると詰まるもの”を先に押さえておくのがコツです。 Day 46〜60:採用と内装が動き始めます。 求人を本格稼働。面接の流れ、評価の観点、初日の研修内容を紙1枚にまとめておくと、ブレません。工事は着工前の最終確認を丁寧に。看板・照明・導線は“通行人の目線”で現地確認を入れると効果が上がります。メニューや価格表、チラシの草案、SNSのアカウント開設も並行で進めましょう。 Day 61〜75:オペレーションの“型”を作ります。 本部研修に参加し、現場の流れを身体で覚えます。マニュアルに自分の言葉のメモを足し、スタッフが読んでも迷わない形に整えます。発注・在庫・清掃・レジ締めのチェックリストをA4で作成。プレオープンの日取りもここで決めて、友人・家族・近隣向けの招待案内を出しておきます。 Day 76〜90:プレオープン→グランドオープン。 プレオープンは“練習試合”です。席数や受付を少し絞り、動線とオペレーションを確認します。うまくいかなかった点はその日のうちに修正。グランドオープンでは、初週の販促にすべてを合わせます。日末のミニ振り返り(客数・客単価・人件費・クレーム・学び)を5分でやり、翌日の改善に回す。ここまで来たら、あとは走りながら整えるだけです。 リスク管理と撤退ライン リスク管理は“怖がるため”ではなく“慌てないため”にやります。まずは早期に気づくための体温計と思いましょう。 体温計はシンプルでOKです。 毎日の客数・客単価・売上、週の人件費率、原価率、クレーム件数。これだけで十分に異変をキャッチできます。業態ごとの“良い数値”は本部が持っていることが多いので、目安の根拠を教えてもらい、店の実情に合わせて微調整します。 撤退ラインは“冷静な自分”が先に決めておきます。 感情でズルズル続けるのが一番つらいです。たとえば「3か月移動平均で売上が基準を下回り、かつ手元資金が固定費の○か月分を下回ったら撤退を検討」など、複数条件の組み合わせで決めます。数値の中身は業態や契約で変わります。ここも断定はしませんが、事前に文書で決めることだけは強くおすすめします。撤退のときに必要な手続き(原状回復、契約上の費用、従業員のケア、在庫の処理)は、契約書と本部のルールで確認しておきましょう。 “守りの備え”も一緒に。 事故・災害・情報漏えい・レジの不具合など、起きてほしくないことはゼロにできません。保険、本部のトラブル時サポート、データのバックアップ、レジの予備運用(手書き伝票の置き場まで決めておく)など、できる範囲で準備しておくと、いざという時に落ち着けます。 まとめ フランチャイズ起業は、気合いより“段取り”です。数字で現実をつかみ、契約で身を守り、現場で確かめる。この3つをそろえれば、迷子になりません。大きな夢はそのままに、やることは小さく、今日できる一歩から始めましょう。 たとえばA4一枚の月次PLをつくる、家族と15分ミーティングをする、気になる本部に3つだけ質問を送ってみる。これだけでも景色が変わります。 不安は悪者ではありません。準備が足りない場所を教えてくれるサインです。売上が揺れても、損益分岐点と感度分析があれば慌てません。契約のツボを押さえていれば、思わぬ出費にも備えられます。現場で“再現性”を確かめておけば、人が入れ替わってもお店は回ります。だから大丈夫。コツコツ整えれば、成功確度はちゃんと上がっていきます。 このメディアは「資料請求で終わり」にしません。加盟者の成功まで並走するのがコンセプトです。迷ったら、本文のチェックポイントに戻って、一つずつ確認しましょう。完璧を目指さなくて大丈夫。7割で動いて、翌日に3割を整える。その繰り返しが、開業後の強さになります。 さあ、数字・契約・現場の順で、今日の一歩を決めましょう。小さく始めて、着実に前へ。応援しています。
-

なぜフランチャイズ起業するのか6W2H
フランチャイズ起業を「願望」から「実行できる計画」に変える道具として、6W2Hはとても心強いフレームワークです。ブランディングやアイデア出しでも使われますが、起業準備に当てはめると、やることが自然と整理されます。難しく考えず、会話するように一つずつ埋めていきましょう。 Why(なぜ) いちばん大切な“動機”です。ここが曖昧だと途中で迷いが増えます。「なぜ今、フランチャイズで起業するのか?」を30秒で言える一文にしておきましょう。例:「家族の時間を守りながら、収入の柱を増やすため」「地元で雇用をつくりたいから」。迷った時の“指針”になります。さらに「やらないこと」も一緒に決めると、誘惑に流されません(深夜営業はしない、無理な値引きはしない、など)。 Where(どこで) 地図の上だけで決めず、必ず歩いて確かめましょう。昼と夜、平日と休日で表情は変わります。人口構成、男女比、生活導線、競合の距離感、駐車のしやすさ。たとえばカフェなら、オフィス街では朝と昼が勝負、住宅地なら午後の滞在需要が強い、という具合に“時間帯の勝ち筋”が見えてきます。オーガニック志向の喫茶を狙うなら、近隣のベビーカー率や健康志向の店舗の有無もヒントです。軽い市場調査でかまいません。狙うエリアと客層を言葉にして、地図にピンを打っておきましょう。 When(いつ) オープン日から逆算して考えましょう。日にちが決まると、資金調達、契約、工事、採用、研修、プレオープンの順番が自然と並びます。細かな日付まで決めなくても大丈夫。「この季節のうちに」「この四半期の中で」など目安を置き、そこから必要な準備の着手タイミングをメモに落とします。本部の標準スケジュールを一度見せてもらい、自分の事情に合わせて微調整しましょう。今週やることを一つだけ決める――それが前進のコツです。 What(何を) 提供する価値そのものです。ここでは“商品名”ではなく“お客さまの変化”で語ってみましょう。例:「忙しい共働き家庭が、夕食づくりの負担を毎日15分減らせる」「在宅ワーカーが午後の集中力をリセットできる場所を提供する」。同じフランチャイズでも、価値の言い方が明確だと、メニュー・価格・販促の決め方が一気に楽になります。 Whom(誰に) ターゲットは“絞るほど伝わる”ものです。広く誰にでも、は結局誰にも届きません。「平日昼にベビーカーで来店する30代のママ」「駅前で短時間のランチを求める20〜40代の会社員」など、顔が浮かぶレベルまで具体化します。人物像が明確になると、立地・営業時間・内装・SNSの言葉づかいまで自然にそろいます。 Who(誰が) フランチャイズ起業の準備をするうえでの作業分担のことを指します。自分でやること、お願いできること、お願いしないとできないことを明確にし、開業までにどういったスケジュールで誰が何をするのか業務の線引きをします。 また、運営していく上でも、「何人雇う必要があるか」「何人配置するのか」なども検討します。 How(どのように) サービス提供のための手段について考えます。同業他社と似たようなことをやっても意味がありません。フランチャイズはある程度制限はありますが、あなたなりのサービス提供方法を検討し、他店、他社との差別化をしましょう。 How much(いくらで) 文字通りお金にかかわること全般のことです。初期投資(加盟金・保証金・内装設備など)と、毎月の運転資金(家賃・人件費・仕入れ・ロイヤリティなど)を分けて考えます。開業前でも、A4一枚でかまいません。月の売上見込み、変動費(原価など)、固定費(家賃や最低限の人件費など)を書き出し、ざっくりの損益分岐点を出してみましょう。 さらに「売上が10%下がったらどうなる?」という“感度チェック”を一回やっておくと、開業後に慌てません。資金が切れないことが最優先です。余裕資金をどのくらい持つかは人それぞれですので、無理のない範囲で確保しておきましょう。 実施プランの構築 6W2Hで輪郭が描けたら、いよいよ開業までのロードマップに落とします。ゴールはシンプル。「誰に」「何を」「いくらで」を、日付と担当つきで動かすだけです。これはフランチャイズに限らず、すべてのビジネスに共通します。まず、今月やることを三つだけ決めます。たとえば「Whyを一文で決める」「候補エリアを昼と夜で一度ずつ歩く」「A4の月次PLを作る」。来月は「本部に3つ質問を送る」「物件を2件見学する」「採用の募集文を下書きする」。この積み重ねが、気づけばオープン直前の“整った状態”をつくります。 事業計画を土台に、継続のための資金、調達の方法、必要な人員と確保の方法まで具体化しましょう。準備の精度が、オープン後の安定と伸びしろを決めます。完璧は目指さなくて大丈夫です。7割で走り出し、翌日に3割を整える。その繰り返しが、あなたの“勝ち筋”になります。
丁寧にヒアリング
厳選したFCをご提案
専門コンサルタントが、お話をお伺いして
あなたに最適なフランチャイズを無料アドバイスします。
丁寧にヒアリング
厳選したFCをご提案
専門コンサルタントが、お話をお伺いして
あなたに最適なフランチャイズを無料アドバイスします。